


デンマーク史の流れを年表でつかもう
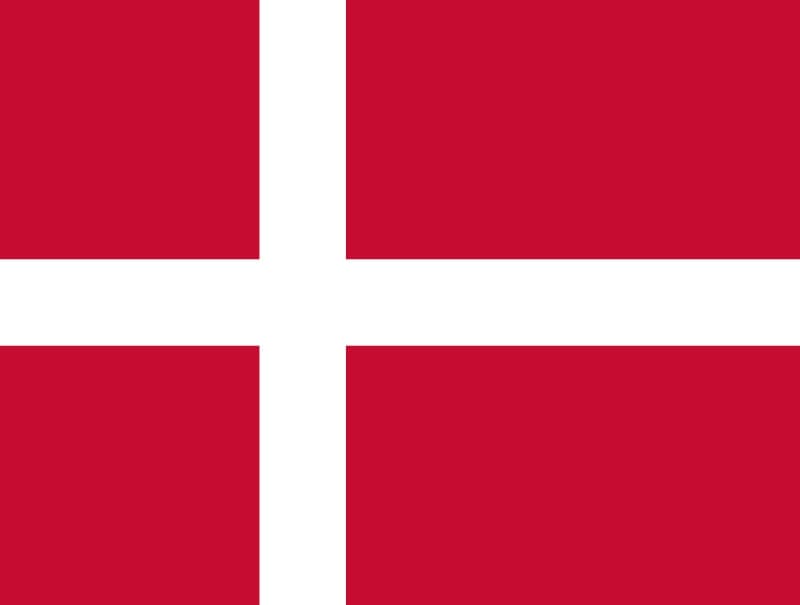
デンマークの国旗

デンマークの国土
| 年代 | 出来事 | 時代 |
|---|---|---|
| 8~11世紀 | ヴァイキング時代、北海・イングランドへ遠征 | 中世 |
| 958年 | ハーラル青歯王がキリスト教に改宗、デンマーク統一 | 中世 |
| 1013年 | クヌート大王がイングランドを征服、北海帝国成立 | 中世 |
| 1035年 | 北海帝国崩壊、イングランドを失う | 中世 |
| 1397年 | カルマル同盟結成、デンマークがノルウェー・スウェーデンと同君連合 | 中世末期 |
| 1523年 | スウェーデンが同盟離脱、デンマーク=ノルウェー連合に | 近世 |
| 1536年 | 宗教改革によりルター派国教化、カトリック勢力排除 | 近世 |
| 1660年 | 絶対王政化、貴族特権の縮小 | 近世 |
| 1814年 | キール条約でノルウェーをスウェーデンに割譲 | 近代 |
| 1849年 | 自由憲法を制定、立憲君主制へ移行 | 近代 |
| 1864年 | 第二次シュレースヴィヒ戦争でプロイセン・オーストリアに敗北 | 近代 |
| 1914~1918年 | 第一次世界大戦では中立を維持 | 近代 |
| 1940年 | ナチス・ドイツに占領されるが王制は維持 | 近代 |
| 1945年 | ドイツ降伏後、王政下で民主主義体制再建 | 現代 |
| 1949年 | NATO創設メンバーとして加盟 | 現代 |
| 1973年 | EC(現EU)加盟 | 現代 |
| 2000年 | 国民投票でユーロ導入を否決、通貨クローネを維持 | 現代 |
| 2022年 | EU共通防衛政策への不参加条項を撤廃(国民投票) | 現代 |
デンマークの歴史詳細
デンマーク(正式名称:デンマーク王国)は 北ヨーロッパの海を挟んでスウェーデンおよびノルウェー、陸上ではドイツと接する地域 に位置する 立憲君主制国家です。国土は ユラン半島および400以上の周辺の島々で構成され、気候区は 大部分が西岸海洋性気候に属しています。首都は 「商人たちの港」、「北欧のパリ」として知られる コペンハーゲン。
この国ではとくに 畜産、農業が発達しており、中でも乳製品、豚肉製品の生産がさかんです。また豊富なエネルギー資源を背景にした石油、天然ガス輸出もこの国の基幹産業となっています。
そんなデンマーク王国の歴史は、10世紀ごろデンマーク王家の始祖ゴーム王に建設されたユトランド半島のイェリング地域から始まるといえます。デンマーク王国はその後14世紀末にスウェーデン、ノルウェーと、デンマークを盟主にしたカルマル同盟を結成し北欧覇権を築きあげます。しかし16世紀初頭のスウェーデンのカルマル同盟離脱、17世紀の三十年戦争における敗北で覇権時代は終わりを迎えます。19世紀のナポレオン戦争の結果、スウェーデンにノルウェーを奪われ、ほぼ現在の領土になりました。第二次世界大戦では一時ドイツに占領されたものの、ドイツ降伏にともない独立を回復し現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなデンマーク王国の歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。
|
|
|
古代デンマーク
前1万2000年頃から現在のデンマークがあるユトランド半島に、人類が居住を始めました。紀元前4000年頃には、新石器時代の文化が発展し、農耕や牧畜が始まりました。この時期には巨石文化も見られ、ドルメンやメンヒルなどの遺跡が築かれました。鉄器時代に入ると、ゲルマン系の部族がこの地に住み着き、独自の文化を形成しました。
紀元前
紀元前のデンマークは、北欧先史時代の文化と社会の発展を象徴する時代です。まず、この時期のデンマークには、青銅器時代(紀元前1700年~紀元前500年)から鉄器時代(紀元前500年~紀元前1世紀)にかけての独特な文化が栄えていました。とりわけ、デンマークでは豊富な考古学的遺跡が発見されており、葬儀のための石造りの墳墓や青銅の武器、装飾品などが出土しています。これらの発見は、当時の人々が自然信仰を持ち、部族間での交易や戦いが頻繁に行われていたことを示唆しています。
また、この時期のデンマークは、バルト海地域を中心とした広域交易ネットワークの一部として重要な役割を果たしていました。琥珀や青銅などの貴重な物資は、このネットワークを通じて他の地域と交換され、デンマークの部族社会に影響を与えたのです。さらに、鉄器時代には、戦闘技術や農業技術の進化も見られ、人々の生活基盤が一層強化されました。戦士たちの墓や武具の供え物なども見つかっており、戦士文化の発展も示されています。
紀元前1世紀頃には、デンマークの社会構造はより複雑になり、徐々に階級制度が形成されていきました。これにともない、リーダーシップを持つ首長が部族を統率する形態も見られるようになります。さらに、ローマ帝国の影響も間接的に及び、南スカンディナヴィア地域での変化のきっかけとなっていきました。
このように、紀元前のデンマークは、自然信仰と戦士文化が交錯し、交易や技術の進展によって社会が進化していく時代だったのです。
前1500年頃 青銅器文化の伝来
前1500年頃、デンマークに青銅器文化が伝来しました。この時期、青銅器は武器、工具、装飾品などに広く使用され、社会の技術水準が大きく向上しました。青銅器の使用は交易によって広がり、デンマークはヨーロッパ全体の交易ネットワークの一部となりました。特に、精巧な青銅製品や金属加工技術の発展は、地域の社会的・経済的な発展に寄与しました。この時期の遺跡や出土品からは、デンマークが高度な技術と豊かな文化を持つ社会であったことがうかがえます。
前500年頃 鉄器文化の伝来
前500年頃には、鉄器文化がデンマークに伝来しました。鉄の使用は、青銅に比べて強度が高く、農具や武器の製造に革新をもたらしました。これにより、農業生産性が向上し、人口増加と社会構造の変化が促進されました。また、鉄器は戦争や防衛にも大きな影響を与え、地域の政治的な変動をもたらしました。鉄器時代の遺跡からは、鉄製の武器や工具、日用品が多く出土しており、この時期のデンマーク社会の高度な技術力と組織力を示しています。
1世紀
1世紀のデンマークは、ローマ帝国の勢力圏外に位置し、ゲルマン民族の一部であるヤストルフ文化に属する人々が暮らしていました。この時期、デンマークはまだ統一された国家ではなく、小さな部族社会が中心で、それぞれが独自の指導者を持ち、独立したコミュニティを形成していました。農業や牧畜が主な経済活動であり、さらにバルト海や北海沿岸での交易も盛んでした。北ヨーロッパの一部として、デンマーク地域はローマの影響を直接受けなかったものの、徐々に南からの文化的影響を受け始めた時代でもあります。
2世紀
2世紀のデンマークは、ゲルマン民族が広く分布していた時期で、ローマ帝国の影響を受けつつも、依然として独自の部族社会が存在していました。この時代、デンマークにはまだ統一された国家がなく、ヤストルフ文化の続きとして、農業や牧畜を基盤とした生活が主流でした。南ヨーロッパからはローマ帝国を通じて武器や装飾品が流入し、北ヨーロッパの鉄器文化の発展に貢献しました。部族間の争いや交易が活発で、戦闘用の装飾品や武器なども多く出土しており、部族社会の戦闘的性質がうかがえます。徐々に、デンマーク地域はローマと接触し、文化的・経済的な影響を受け始めた時代といえます。
3世紀
3世紀のデンマークは、引き続きゲルマン部族が支配していた地域であり、部族社会はより複雑化していきました。ヤストルフ文化からローマ鉄器時代へと移行するこの時代には、鉄器の使用が広がり、武器や農具の製造技術が進化しました。ローマ帝国の北方拡大が停止したため、デンマークはローマの直接支配を受けませんでしたが、交易を通じてローマの影響を受け続けました。この時期には、ゴート族やアングル族、サクソン族などのゲルマン諸部族がヨーロッパ全土で移動を開始しており、デンマークでもその影響を受け、部族の動きが活発化しました。こうした部族の動向が後のヴァイキング時代の基盤を形成していくことになります。
4世紀
4世紀のデンマークは、ローマ鉄器時代後期にあたり、ゲルマン民族の動きがさらに活発化した時期です。この時代、デンマークにはまだ中央集権的な国家はなく、複数の部族が独立した社会を形成していました。ゲルマン民族の一部が西ローマ帝国の境界に迫り、ヨーロッパ全土で大規模な移動(ゲルマン民族の大移動)が起こる中で、デンマークも影響を受けました。特に、ユトランド半島では、アングル族、サクソン族、ジュート族などが台頭し、彼らの一部は後にブリテン島へ移住します。このような移動は、デンマークの社会や経済構造に変化をもたらし、交易や戦闘による新たな文化の交流が進みました。また、埋葬習慣や装飾品の変化からも、地域内での権力構造の変化がうかがえます。
375年 ゲルマン民族の大移動
ゲルマン民族の大移動が始まり、ゲルマン民族の一派であるデーン人がデンマークの地に到来する。
|
|
|
中世デンマーク
現在のデンマークは、中世(8世紀~11世紀後半)の「バイキング時代」に活躍した、バイキングの1支族デーン人の国で、クヌード大王(在位:1018年-1035年)による北海帝国建設が起源と言われています。クヌード大王の死後、北海帝国は崩壊してしまいましたが、14世紀末、ノルウェー・スウェーデンとの間で、デンマークを盟主としたカルマル同盟が結成されると、北欧全域を支配下におさめるヨーロッパの大国として君臨しました。しかし、カルマル同盟は内部の対立や外部の圧力により16世紀初頭に解体。その後、デンマークは独立国家として存続し、絶対王政の時代を経て、徐々に近代化への道を歩むこととなりました。デンマークは商業と海軍力を強化し、バルト海周辺での影響力を維持しつつ、近代国家としての基盤を築いていきました。
5世紀
5世紀のデンマークは、「民族大移動時代」の影響を強く受け、ゲルマン部族の移動と再編が顕著になった時期です。特に、ユトランド半島に住むアングル族やジュート族などは、この時期にブリテン島へと移住を開始し、後のイングランド王国の基盤を築くことになります。この移動により、デンマーク内でも人口の変動や権力構造の再編が生じました。
一方、デンマークに残った部族社会では、農業や牧畜を中心とした生活が続きつつも、戦闘のための武器製造や防衛体制が強化されました。また、考古学的な発見から、王権の萌芽とも言えるような集団指導者の存在や、地域ごとの小規模な王国が形成され始めたことも示されています。
このように5世紀のデンマークは、後のヴァイキング時代へとつながる動乱と変革の時代だったのです。
6世紀
6世紀のデンマークは、ゲルマン部族社会から徐々に統治構造が発展し、地域ごとの王国が形成され始めた時期です。この時代、ユトランド半島と周辺の島々には、小規模な王国や部族連合が存在し、これらが後にデンマーク統一へとつながる基盤を作っていきます。6世紀末には、考古学的証拠からも、強力な支配者層の出現や、王族墓地の存在が確認され、社会的階層がより明確になってきたことがわかります。これに伴い、集落の防衛施設や、金製品、武器などの富を象徴する物品も増加し、権力の集中が進んでいきました。また、デンマークはスカンディナヴィア全体での交易ネットワークの一部として、他の北欧地域やバルト海沿岸とも接触を持ち、文化的影響の受け渡しが活発化しました。これらの要素が、後のヴァイキング時代の拡大と進展を予兆させる動きを示しています。
7世紀
7世紀のデンマークは、北欧の他の地域と同様に、まだ前ヴァイキング時代(Vendel時代)にあたります。この時期、デンマークの領域は小さな部族社会に分かれており、統一された国家は存在していませんでした。デンマークは北欧の交易と海上活動の中心として、バルト海や北海沿岸の部族との交流が盛んでした。多くの考古学的発見が示すように、地域の人々は鉄器、宝飾品、船を製造し、交易と略奪の両方を行っていたと考えられます。
デンマークの領域内での宗教は多神教で、神々への崇拝が盛んでしたが、後のヴァイキング時代の影響を受けて、徐々にキリスト教が浸透していく兆しも見られ始めています。
7世紀はデンマークがヴァイキング時代の到来に向けて徐々に変容していく、重要な準備期といえるでしょう。
8世紀
8世紀のデンマークは、ヴァイキング時代の幕開けとして重要な時期です。この時代、デンマークは統一への動きが進み、王権が徐々に確立されていきました。考古学的な証拠から、8世紀後半にはデンマークの初期王朝が成立し、ハーラルド・ヒルダンド(「歯の破壊者」として知られる)が王として登場したことが示唆されています。
とりわけデンマークのヴァイキングは、イギリス諸島やフランク王国をはじめとするヨーロッパ各地への遠征を開始。特に、793年のリンディスファーン修道院襲撃は、デンマークを含む北欧ヴァイキングの影響力が初めて歴史に記録された事件として有名です。海洋技術の発展とロングシップ(長船)の使用により、デンマークはヨーロッパ全土にわたる交易と略奪の中心地となり、その勢力は拡大していきました。
9世紀
9世紀のデンマークは、ヴァイキング時代の全盛期にあたる重要な時代です。この時期、デンマークは国家としての統一を進め、中央集権的な王国が形成されました。ゴーム老王(Gorm the Old)が登場し、デンマーク王国の支配者としてその権威を確立し始めました。彼の治世は10世紀初頭にまで続き、デンマーク王朝の基盤を築きました。
9世紀のデンマークのヴァイキングは、ヨーロッパ各地での征服や略奪を活発に行っていました。特に、イングランドやフランスへの遠征が増え、イングランドの「大異教軍(Great Heathen Army)」として知られる大規模な侵攻はデンマーク出身のヴァイキングによるものでした。この侵攻はイングランドの支配者層を揺るがし、一時的にデンマークのヴァイキングが広範囲にわたってイングランドを支配することに成功しました。また、フランク王国(現在のフランス)にも進出し、パリ包囲戦(845年)などの重要な出来事も起こりました。
同時に、デンマークはキリスト教化の影響を徐々に受け始め、9世紀末にはその宗教的変革が政治的な統合にもつながる兆しを見せ始めていました。
このように、9世紀のデンマークは、ヴァイキング活動を通じて軍事的・政治的に台頭する一方で、新しい宗教的潮流にも直面する複雑な時代でした。
10世紀
10世紀のデンマークは、王国の統一とキリスト教への改宗が進む時代で、デンマーク史において極めて重要な転換期です。この時期に最も重要な人物は、デンマークの初代「王」とされるハーラルド・ブルートゥースです。彼は、父であるゴーム老王の後を継ぎ、デンマークを初めてキリスト教国家として公式に宣言しました。ハーラルドはまた、国内の部族を統一し、国土を強固にまとめ上げました。
ハーラルドは、キリスト教の受容を象徴する石碑であるイェリング・ストーンズ(Jelling Stones)を建てたことで知られています。これらの石碑は、デンマークのキリスト教化と王国の統一を記念するもので、デンマーク文化の重要な遺産となっています。
また、この時期には、デンマークのヴァイキング活動が続きましたが、その形態が変化しました。特に、イングランドへの遠征が続き、デーン人(デンマークのヴァイキング)によるイングランドの征服が進行しました。最終的に、1013年にはハーラルドの息子であるスヴェン・フォークベアードがイングランド王位を獲得し、デンマークとイングランドの二重王国が形成されることになります。
このように、10世紀のデンマークは、王国の統一とキリスト教への改宗、さらに国際的な影響力の拡大という歴史的な転換期を迎えた時代でした。
11世紀
11世紀のデンマークは、王国の政治的・文化的な発展と、スカンディナヴィア地域での影響力の拡大が特徴的な時代です。この時代の中心的な人物は、クヌート大王(クヌート1世)であり、彼はデンマーク、イングランド、ノルウェーを統治する「北海帝国」を築き上げました。クヌートの治世は、デンマークの最盛期の一つとされ、彼の政策によって3つの王国は安定した統治がなされました。
クヌート大王の支配下では、デンマークはキリスト教の強化が進みました。彼は教会を支援し、聖職者を重用することで、デンマークの統治を強化しました。また、彼の死後、息子たちによって支配は続いたものの、やがてイングランドとノルウェーの支配は失われ、デンマークの影響力は縮小していきました。
11世紀後半には、デンマーク内部での権力闘争が激化し、王位をめぐる争いが相次ぎました。最終的に、スヴェン2世エストリズセンの子孫たちが王位を確立し、国内の統治が安定化されていきました。
このように、11世紀はデンマークが広大な領域を支配し、国際的な影響力を持つ一方で、内外の変動によってその政治的構造が大きく変化した時代でした。
1110年代 クヌート2世のイングランド侵攻
デンマーク王クヌート2世がイングランドに侵攻。デンマークからイングランド、ノルウェーにまで版図を広げ北海帝国を築き上げる。しかしクヌート2世の死後すぐに崩壊。
1047年 スヴェン2世の即位
スヴェン2世がデンマーク王として即位。彼の治世は、国内の統一と強化が進められた時期であり、スヴェン2世は北欧全体におけるデンマークの影響力を拡大しようと努めた。また、彼はキリスト教の普及を促進し、デンマークの宗教的統一を図った。スヴェン2世の治世中に、デンマークは政治的にも文化的にも発展し、後の歴史における強国としての基盤を築くこととなった。
12世紀
12世紀のデンマークは、内政の改革とキリスト教のさらなる浸透、王権の確立を中心に発展した時代です。この時期、デンマークは王位継承をめぐる内紛や、隣国との戦争が頻発しました。前半は内乱が続き、
- スヴェン3世
- カヌート5世
- ヴァルデマー1世
など複数の王が争う「三王時代」が訪れ、国内は分裂状態に陥りました。
しかし、12世紀後半に登場したヴァルデマー1世(ヴァルデマー大王)が国内を統一し、強力な王権を確立しました。彼の治世において、デンマークは聖職者アブサロンと協力し、教会と国家の結びつきを強め、中央集権化を推進しました。また、バルト海沿岸の異教徒スラヴ人との戦いを展開し、デンマークの影響力をバルト海地域へ拡大しました。
さらに、12世紀はデンマークの経済的・文化的発展の時期でもあります。都市の形成が進み、特にルンドやロスキレなどの都市が商業や宗教の中心地として栄えました。教会の建設も盛んになり、ゴシック建築の影響を受けた教会堂や大聖堂が多く建設されました。
このように、12世紀のデンマークは内乱の時代を経て、王権の強化と宗教的、文化的な発展が進んだ時代となりました。
1157年 ヴァルデマー1世の即位
ヴァルデマー1世が王位につき、王位継承問題で混乱していたデンマーク王国の再建に動き出す。彼は内戦を終結させ、王国の統一を確立し、中央集権的な統治体制を強化した。また、ヴァルデマー1世はデンマークの軍事力を強化し、バルト海周辺の領土拡大を推進した。彼の治世は、デンマークの安定と繁栄を取り戻すための重要な時期であり、後のデンマークの繁栄の基礎を築いた。また、彼の支持のもとで、教会と国家の関係が強化され、キリスト教の影響力が一層高まった。
13世紀
13世紀のデンマークは、王権の絶頂期と衰退の時代を迎えます。この時期、デンマークはバルト海地域での影響力をさらに拡大し、一時期はエストニアやノルウェーなどの周辺領域を支配しました。最初の王であるヴァルデマー2世(ヴァルデマー勝利王)の治世(1202年~1241年)は特に注目される時期です。
ヴァルデマー2世はバルト海沿岸の異教徒への十字軍を主導し、1219年にはエストニアの領有を確立し、タリンの街を創設しました。また、彼の治世では国内の法整備が進み、「ユトランド法典」などの法典が編纂されました。これにより、王権は中央集権化され、デンマーク社会の統治機構が強化されました。
しかし、彼の晩年には政治的な安定が崩れ、ドイツの諸侯や他のスカンディナヴィア諸国との戦争が続きました。ヴァルデマー2世の死後、後継者たちの間で王位継承を巡る争いが再び起こり、国内は混乱します。さらに、1261年にはダグマーの乱が発生し、領土の一部を失う結果となりました。
13世紀末には、貴族や教会の力が強まり、王権は弱体化します。1290年代にはエーリク5世やエーリク6世による強権的な統治が試みられましたが、貴族と都市の対立が激化し、国内の分裂が深まりました。
このように、13世紀のデンマークは拡大と崩壊が混在する時代であり、王権と貴族勢力のバランスが大きく変動した時期でした。
1241年 ヴァルデマー2世の死去
ヴァルデマー2世の治世のもと、デンマークは安定し勢力を拡大したが、彼の死により再び王位継承問題で揉め混乱の時代に突入した。ヴァルデマー2世は、デンマークの領土を大幅に拡大し、法制度の整備や経済の発展を推進した名君として知られていた。彼の死後、王位継承をめぐる争いが勃発し、国内は再び不安定な状態に陥った。この混乱はデンマークの政治的・経済的な後退を招き、次の安定期までの間、国家は内戦や領土の喪失に苦しむこととなった。
14世紀
14世紀のデンマークは、政治的混乱と改革、そして地域的な連携の時代でした。デンマークはこの時期、内政の不安定さと経済的困難に直面し、また隣国との戦争や同盟の変動が続きました。王権は貴族の台頭により弱体化し、その結果、中央集権的な統治が揺らぎます。
デンマークはこの時期、複数の王による断続的な治世を経験します。エーリク6世とその弟クリストファ2世の治世では、国内の不安定さが続き、クリストファ2世は1320年に貴族たちとの協定「ハンドフェスト」を承認し、王権を大幅に制限されました。彼の治世中にはデンマークが一時的に破綻し、王国は分裂状態に陥ります。
そんな中1340年、ヴァルデマー4世アーターダグが王位に就き、デンマークの再統一を目指します。ヴァルデマー4世は、失われた領土を再統合し、経済と軍事の改革を推進しました。彼の治世中にデンマークは再び強国へと復帰し、バルト海沿岸での影響力を回復しました。しかし、彼の死後に後継者問題が再び浮上します。1380年にはデンマークとノルウェーの王位が統合され、続いて1397年にはカルマル同盟が結成され、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3王国が統合されることになります。この同盟はマルグレーテ1世によって主導され、スカンディナヴィアの歴史に新しい枠組みをもたらしました。
こうして、14世紀のデンマークは内紛と改革の中で新しい政治的連携を形成し、北欧全体の結束を目指す時代となりました。
1340年 ヴァルデマー4世の即位
ヴァルデマー4世が王位につき、デンマークの混乱収拾に努める。見事に国力を回復させ、「アッテルダーク(再興王)」と称された。彼は財政を再建し、領土を回復し、強力な中央集権を確立した。彼の治世は、デンマークの安定と繁栄を取り戻すための重要な時期となり、後の北欧におけるデンマークの支配を強化する基盤を築いた。
1380年 オーロフ2世の即位
ヴァルデマー4世の死後、孫のオーロフ2世が王位を継ぐ。この時ノルウェー王位も継承したことで、デンマークとノルウェーの同君連合が形成される。オーロフ2世の治世は短かったが、この同君連合は北欧の政治的統合の第一歩となり、後のカルマル同盟の基礎を築いた。
1397年 カルマル同盟の締結
デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3王国間でデンマークを盟主としたカルマル同盟が締結。デンマークは事実上北欧全土を支配下に治めた。この同盟は、女王マルグレーテ1世の指導のもとで成立し、北欧の政治的安定と統一を目指した。同盟により、デンマークの影響力は大いに強化され、北欧地域の統一と繁栄が進められた。しかし、スウェーデンの独立志向や内部の権力争いにより、後に同盟は緩やかな形での統治となり、最終的には1523年にスウェーデンが脱退することで崩壊した。
15世紀
15世紀のデンマークは、カルマル同盟のもとで北欧全体の統合と内部抗争が繰り広げられた時代です。カルマル同盟は1397年に結成され、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3王国を一人の君主が統治する形で成立しました。デンマークはこの同盟の主導的な立場にあり、特に女王マルグレーテ1世の影響力が強く、15世紀の初頭にはその権力が頂点に達しました。
しかし、15世紀を通じてカルマル同盟内での緊張が高まります。スウェーデン貴族はデンマークの支配に不満を抱き、独立の動きを強めました。これにより、同盟内での内部対立が深まり、数度にわたるスウェーデンの反乱が起こり、デンマーク王クリスチャン1世は、同盟の安定を図りながらも反乱運動と対峙しなければなりませんでした。
その後クリスチャン1世の治世(1448年~1481年)では、デンマークの王権強化と貴族との権力争いが続きました。彼はロスキレ大聖堂の建設やコペンハーゲン大学の設立など、文化面での発展にも力を入れましたが、経済低迷やスウェーデンとの戦争が財政を圧迫し、結果としてデンマーク国内の不満を高めました。
15世紀末には、スウェーデンが再び独立を主張。同盟は次第に崩壊の兆しを見せ始め、最終的に、カルマル同盟は16世紀に完全に解体されることになるのです。
このように15世紀のデンマークは北欧の統合を試みる一方で、内部対立と外部戦争に悩まされる時代でした。
1448年 オルデンブルク朝の創始
クリストファ3世が死去し、ホルシュタインのオルデンブルク伯がデンマーク王として即位。後にデンマークをヨーロッパ有数の大国にまでのし上げるオレンボー朝が始まる。
1460年 スレースヴィ公国とホルシュタイン公国の同君連合成立
スレースヴィ公国とホルシュタイン公国の同君連合が成立。デンマーク王クリスチャン1世が両公国の支配者となり、デンマークと両公国の関係が深まる。この同君連合により、デンマークはドイツ北部との結びつきを強化し、バルト海地域における政治的影響力を拡大した。スレースヴィとホルシュタインは、デンマークの経済や軍事にとって重要な地域となり、デンマークの領土拡大と安定化に寄与した。この同君連合は、19世紀に至るまで続き、デンマークとドイツの関係に長期的な影響を与えることとなった。
|
|
|
近世デンマーク
近世デンマーク(16世紀から18世紀)は、カルマル同盟の解体後、独立国家として再編され、絶対王政が確立されました。この時期、デンマークは商業と海軍力を強化し、バルト海周辺での影響力を拡大しました。特に、クリスチャン4世(在位:1588年-1648年)の治世下で、首都コペンハーゲンの発展や経済改革が推進されました。
また、デンマークは三十年戦争(1618年-1648年)に参戦し、ドイツ北部での領土拡大を試みましたが、成功しませんでした。17世紀後半にはスウェーデンとの戦争が続き、スコーネ戦争(1675年-1679年)や大北方戦争(1700年-1721年)を経て、デンマークは領土を失うことになりました。
18世紀には、啓蒙時代の影響を受けて農業改革や教育制度の整備が進み、社会の近代化が図られました。デンマークはこの時期、海外植民地の獲得にも力を入れ、グリーンランドや西インド諸島などの地域を支配。これにより、デンマークは国際的な貿易と影響力を拡大し、ヨーロッパの主要国の一つとして位置づけられるようになったのです。
16世紀
16世紀のデンマークは、宗教改革や北欧での覇権争いなど、大きな変動が起こった時代です。この時期、デンマークはカルマル同盟の崩壊後、再びスカンディナヴィアでの主導権をめぐる争いに巻き込まれました。また、宗教改革の波がデンマークにも及び、社会や政治構造にも大きな影響を与えています。
デンマークでは、クリスチャン2世の治世(1513年から1523年)が混乱の始まりでした。彼はスウェーデンを再びカルマル同盟の下に統一しようと試みましたが、1520年のストックホルムの血浴による反発を招き、結果的にスウェーデンの独立とデンマーク王位の失脚につながりました。その後、フレゼリク1世が即位し、デンマークは内政の安定を図りました。
16世紀の中頃には、宗教改革がデンマークにも到来し、ルター派のプロテスタントが広まりました。フレゼリク1世の息子クリスチャン3世は1536年にデンマークをルター派に改宗させ、カトリック教会の財産を没収、国家主導の教会を設立しました。これにより、教会と国家の権力構造が大きく変化し、王権の強化が進んだのです。
また、この時代には北方七年戦争(1563年から1570年)が勃発し、デンマークとスウェーデンはバルト海の支配権をめぐって激しく争いました。この戦争は最終的に引き分けに終わり、両国ともに大きな損害を受けましたが、デンマークはスカンディナヴィアでの影響力を維持することに成功しました。
16世紀のデンマークは、宗教改革による社会変革と北欧での覇権争いを経験し、国としてのアイデンティティと統治体制を再構築する時代でした。
1520年 ストックホルムの血浴
デンマーク支配に抵抗するスウェーデン人を粛清するが(ストックホルムの血浴)、これが逆に独立運動に火を付けることとなり、カルマル同盟は崩壊。責任を問われデンマーク王クリスチャン2世は廃位に追い込まれ、代わりにフレゼリク1世が擁立された。
1525年 宗教改革の始まり
ルターの宗教改革の影響が及ぶようになり、ハンス・タウセンによりルター派(プロテスタント)の布教が始まる。
1534年 伯爵戦争
フレゼリク1世が死去(1533年)し、クリスチャン2世が復位を目論み伯爵戦争を起こすも、クリスチャン3世に倒される。その後クリスチャン3世はデンマーク王に即位したのち、ルター派を国教とする宗教改革を実施した。
1537年 デンマーク=ノルウェーの成立
ノルウェーを完全に支配下に置き、デンマーク=ノルウェーを成立させる。この統合により、ノルウェーはデンマーク王国の一部として統治され、中央集権的な管理が強化された。デンマーク=ノルウェーは政治的、経済的、軍事的に密接な関係を持ち、北欧における強力な連合国家として機能した。この連合は、文化的交流や経済的発展を促進し、両国の繁栄に寄与した。
デンマーク=ノルウェーは1814年まで続き、スウェーデン=ノルウェーの連合が成立するまで、北欧の重要な政治勢力として存在し続けました。
1559年 フレゼリク2世の即位
クリスチャン3世が死去し、フレゼリク2世が王位につく。フレゼリク2世の治世は、デンマークの国内安定と経済発展が進んだ時期であり、特にバルト海貿易の拡大に力を入れた。また、彼の治世中に宗教改革が進行し、プロテスタント信仰が国内に定着した。フレゼリク2世は外交面でも積極的に活動し、北欧諸国との関係強化に努めた。彼の統治はデンマークの繁栄と安定をもたらし、次のクリスチャン4世の治世に続く重要な基盤を築いた。
1563年 北方七年戦争の勃発
フレゼリク2世が、伸張を続けるスウェーデンを脅威とみて、宣戦布告し北方七年戦争を開始する。最終的には「シュテッティンの和約」が結ばれ引き分けとなり、スウェーデン再征服という当初の目的は果たされなかった。
1588年 クリスチャン4世の即位
クリスチャン2世の死後、息子のクリスチャン4世が王位を継ぐ。クリスチャン4世の治世はデンマーク=ノルウェーの黄金時代とされ、特に経済的・文化的な発展が顕著であった。彼は積極的に国内外の貿易を推進し、都市の整備や産業の発展を図った。また、科学や芸術の支援にも力を入れ、デンマーク文化の隆盛を支えた。しかし、30年戦争における軍事的失敗は、彼の治世における大きな困難となり、デンマークの国力に打撃を与えた。それでも、クリスチャン4世はデンマークの歴史において重要な王として記憶されている。
17世紀
17世紀のデンマークは、スカンディナヴィア地域での覇権をめぐる戦争と、絶対王政の確立が進んだ時代です。まず、デンマークは当時、ノルウェーと共にデンマーク=ノルウェー連合王国を形成し、バルト海や北海の支配権を維持しようと努めましたが、スウェーデンとの間で幾度も戦争を繰り返しました。
そして17世紀初頭のカルマル戦争(1611年から1613年)では、デンマークはスウェーデンとの間で勝利を収め、一時的にその優位を保ちました。しかし、その後の三十年戦争(1618年から1648年)への介入は大きな失敗となり、国力を大きく消耗。さらに、1643年から1645年にかけてのトルステンソン戦争でデンマークはスウェーデンに敗北し、南スウェーデンの領土を割譲することになりました。
このような失敗を経て、デンマークは国内改革に着手。フレデリク3世の治世下で、1660年に貴族の特権を制限し、絶対王政を確立しました。つまり国王が直接支配する中央集権的な体制が整い、行政の効率化や財政改革が進められ、デンマークは再び強国としての基盤を固めていくのです。
17世紀の終わりには、スウェーデンとの間で再び戦火が交えられましたが、大北方戦争(1700年から1721年)の序盤にデンマークは苦戦を強いられることになります。
このように17世紀のデンマークは戦争と改革が交錯する中で、絶対王政の成立を通じて新しい国家体制を構築していった時代でした。
1620年 デンマーク初の植民地建設
クリスチャン4世により、インド南岸のトランケバール(現インド・タミルナドゥ州)に、デンマーク初の植民地が建設された。この植民地建設は、デンマークが海外植民地帝国を築く第一歩となり、インド洋地域での貿易活動を拡大するための重要な拠点となった。トランケバールは香辛料、織物などの貿易で栄え、デンマークの経済的繁栄に寄与した。
1643年 トルステンソン戦争の勃発
スウェーデンとトルステンソン戦争を起こし敗れる。この戦争は、スウェーデン王グスタフ・アドルフの指揮官レンナート・トルステンソンによって引き起こされ、デンマークは戦争に敗北し、領土と政治的影響力を大きく失った。戦争の結果、デンマークはブレムセブル条約を締結し、スウェーデンに領土を割譲することを余儀なくされた。この敗北はデンマークの国力に深刻な影響を及ぼし、北欧におけるスウェーデンの覇権を確立する一因となった。
1657年 カール・グスタフ戦争の勃発
クリスチャン4世の死後フレゼリク3世が即位。スウェーデンとのカール・グスタフ戦争を戦うも敗れ、重要な勢力圏を大幅に消失し、ヨーロッパの小国に没した。この敗北により、デンマークはロスキレ条約を締結し、スウェーデンに大規模な領土を割譲することとなった。
1660年 絶対王政の確立
フレゼリク3世は、それまでの選挙王制から世襲王政へと体制を変え、絶対王政を確立した。この改革により、王権は大幅に強化され、貴族の権力を抑制することで、中央集権的な統治体制が整えられた。
1683年 デンマーク法の制定
フレゼリク3世の跡を継いだクリスチャン5世の下で、デンマーク法が制定された。この法典は、デンマークの統治と法律の基礎を確立し、近代的な法治国家としての基盤を築く重要な一歩となった。デンマーク法は、行政、司法、社会制度の整備において画期的な役割を果たし、法の下での平等と公正を推進した。
1700年 大北方戦争の勃発
大北方戦争が起こり、デンマークは反スウェーデン同盟側として参戦したが、特に戦果は得られず、逆にバルト海の覇権をロシアに握られてしまった。
18世紀
18世紀のデンマークは、戦争と改革を通じて国家の近代化を進める時代でした。この時期、デンマークは大北方戦争(1700年から1721年)に参加し、スウェーデンとの間で再び激しい戦争を繰り広げました。大北方戦争では最初こそ苦戦を強いられたものの、最終的にはロシア、ポーランド、プロイセンとの同盟関係が強まり、デンマークは戦後、スカンディナヴィアでの影響力を取り戻しました。
大北方戦争後、フレデリク4世とクリスチャン6世の治世を通じて、国内の改革が推進されました。特に農業政策や軍事改革が進み、農奴制の廃止に向けた動きが徐々に見られ始めています。そしてフレデリク5世の治世では、啓蒙思想の影響を受けた改革がさらに進行。彼のもとで法制度の整備や経済政策の改善が行われ、特に商業と工業の発展が促進されたことが重要ですね。
18世紀半ばには、ドイツ出身の外務大臣ストルーエンセが実権を握り、短期間で急進的な改革を推進。彼の政策は専制政治の弱体化と自由主義的な社会改革を目指すものでしたが、貴族たちの反発を招き、最終的には失脚します。この事件は、デンマークにおける啓蒙主義の限界を示すものとなりました。
18世紀の終盤には、アメリカ独立戦争やフランス革命の影響を受け、デンマークでも政治的な変革の必要性が高まります。そしてフレデリク6世の治世に入ると、デンマークはヨーロッパの大国間で中立を保つ政策を取りつつ、国内での改革に力を入れました。そんな情勢での1800年、デンマークの農奴制が完全に廃止され、農業改革が完成されたのです。
18世紀のデンマークは、戦争と改革を通じて絶対王政の体制を揺るがしつつも、近代国家としての基盤を築くための重要な時期となりました。
1730年 農業改革
クリスチャン6世の時代に深刻な農業危機が発生し、様々な農業改革が行なわれた。農業生産性の向上を目指し、土地の再分配や農業技術の改良が推進された。これにより、農民の生活条件が改善され、デンマークの農業基盤が強化された。また、農村地域のインフラ整備も進められ、農業改革はデンマークの経済全体に対してもプラスの影響をもたらした。この改革は、後の農業発展と安定した食糧供給の基礎を築くこととなった。
1772年 反体制のクーデター発生
精神疾患を患っていたクリスチャン7世の代わりに、医者のストルーエンセが摂政となり実権を握る。しかし彼の改革は民衆の大きな反発を呼び、クーデターが発生。ストルーエンセは失脚、処刑された。
|
|
|
近代デンマーク
一時はヨーロッパ屈指の勢力圏を築き上げたデンマークですが、激動のヨーロッパ情勢で覇権を維持するのは難しく、16世紀にはスウェーデンが分離、19世紀にはデンマークとノルウェーとの同君連合も解消されたことで、ほぼ今と同じデンマークの領土になりました。一時は北欧全域を支配するほどの力を持っていたデンマークですが、19世紀後半の第二次シュレースビッヒ戦争でプロイセンとオーストリアに敗北し、スカンジナビア半島とシュレースビッヒ公国及びホルシュタイン公国を失ってしまいます。北欧の大国としての地位を失った瞬間でした。
以降、デンマークは中立の立場を重視し、戦争にはあまり首をつっこまなくなりました。しかし第二次世界大戦では、中立を表明していたにも関わらず、ドイツに占領されてしまいます。そういった反省もあり、安全保障のための伝統的な中立政策を放棄することを選択し、戦後は北大西洋条約機構(NATO)の創立メンバーとして原加盟国となりました。
このように他の北欧諸国と歩調を合わせたことで、戦後デンマークは順調に経済成長を遂げていきました。今では国民総所得で世界5位と、北欧の先進国として十分な存在感を放っています。
19世紀
19世紀のデンマークは、政治的・社会的変革が相次いだ時代であり、絶対王政から立憲君主制への移行、戦争による領土の喪失、そしてナショナリズムの高まりを特徴とする時代です。まず、ナポレオン戦争の影響を強く受けたデンマークは、フランスと同盟を結び、英国を中心とする連合国と敵対することになりました。これにともない、1807年にはコペンハーゲンがイギリス海軍による大規模な砲撃を受け、デンマーク艦隊は壊滅状態となりました。また、1814年のキール条約によってノルウェーをスウェーデンに割譲することを余儀なくされ、長年続いたデンマーク=ノルウェー連合王国が崩壊するという大きな転機を迎えました。
その後の時期、デンマークは国内の政治改革を進め、1849年には自由主義的な憲法が制定され、絶対王政は終焉を迎え、立憲君主制が確立されます。この新しい憲法は、議会政治の発展とともに国民の政治参加を広げることとなり、デンマークは新たな近代国家としての歩みを始めました。とりわけ、農業改革が進行し、農民の権利が拡大されたことは、デンマーク社会における重要な変化を象徴しています。農奴制が完全に廃止され、農村経済が活性化されるとともに、地方自治も強化されることで、デンマークの地域社会は活気を取り戻していきました。
しかし、19世紀後半に入ると、デンマークはシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題に直面します。シュレースヴィヒ公国とホルシュタイン公国を巡るこの領土問題は、ドイツ民族主義の高まりと絡み合い、二度の戦争を引き起こしました。第一次シュレースヴィヒ戦争(1848年から1851年)では勝利を収めたものの、1864年の第二次シュレースヴィヒ戦争ではプロイセンとオーストリアに敗れ、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン両公国を失いました。この敗北により、デンマークの国力は大きく減退し、以後、バルト海地域においても中立的な立場を取る方向へと転じることになります。
このように、19世紀のデンマークは戦争と領土の喪失、そして政治的な近代化と社会変革が交錯する中で、国家の新たな方向性を模索する時代だったのです。
1801年 イギリス軍によるコペンハーゲン攻撃
ナポレオン戦争が始まる。イギリスは武装中立の立場をとるデンマークを脅威とみており、コペンハーゲンを攻撃し、デンマーク海軍を破壊した。
1813年 ナポレオン戦争に参戦
デンマークはナポレオン戦争における中立の立場を放棄。フランス勢力として参戦。莫大な戦費を費やし、国家財政が破綻した。
1814年 キール条約の締結
イギリス、スウェーデンと、ナポレオン戦争の敗戦国デンマークとの間で、キール条約が結ばれた。この条約で、デンマークはノルウェーを手放すこととなった。
1849年 立憲君主制に移行
国内で国民自由主義(ナショナルリベラル)の気運が高まり、1948年革命の後、デンマークは立憲君主国へと体制が移行。成年男子の参政権、報道の自由、結社の自由が認められるなどした。
1845年 イギリスにインド植民地を売却
デンマークは、インド南部にあった植民地トランケバールをイギリスに売却。この売却は、デンマークの海外植民地政策の縮小を意味し、インド洋地域におけるイギリスの影響力をさらに強化する結果となった。経済的な困難や維持費用の問題から、デンマークはインド植民地を手放す決断をした。この売却により、デンマークはヨーロッパ内の政策により注力するようになり、国内の経済改革や社会政策に力を入れることとなった。
1864年 デンマーク戦争の勃発
第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争(デンマーク戦争)の結果、デンマークは肥沃な土地を抱えるシュレースヴィヒ公国とホルシュタイン公国を手放すこととなった。
1873年 スカンディナヴィア通貨同盟の締結
デンマークはスウェーデンとの間にスカンディナヴィア通貨同盟を締結。この同盟により、デンマークとスウェーデンは金本位制に基づく共通の通貨単位クローナを導入し、両国間の貿易と経済活動を促進した。スカンディナヴィア通貨同盟は、後にノルウェーも参加することでスカンディナヴィア全域に広がり、地域経済の統合と安定に寄与した。この同盟は、北欧諸国間の経済的協力と相互信頼の強化を象徴するものであり、地域の経済成長と繁栄を支える基盤となった。
20世紀
20世紀のデンマークは、戦争と平和、社会福祉国家の確立という大きな転換を経て、近代国家としての成熟を遂げた時代です。まず、第一次世界大戦中、デンマークは中立を維持し、戦火を避けることに成功しました。しかし、その後の戦間期には国内の政治構造が変化し、社会民主党と自由党の連立による安定した政権が確立されました。
第二次世界大戦中、デンマークは再び中立を宣言しましたが、1940年にはドイツ軍による侵攻を受けます。抵抗は最小限に抑えられましたが、1943年にはナチスへの抵抗運動が活発化し、多くのユダヤ人がスウェーデンへと避難しました。戦後、デンマークは北欧モデルを推進し、1953年の憲法改正によって福祉国家の基盤を確立します。これにより、医療や教育、年金制度などの分野で手厚い社会保障が整備され、国民の生活水準が大きく向上したことは重要です。
冷戦期には、デンマークはNATOに加盟し、西側陣営としての立場を明確にしました。また、1973年には欧州経済共同体(EEC)にも加盟し、経済的な結びつきを強化。デンマークはより広いヨーロッパの枠組みの中で、自国の経済的・政治的な役割を再定義するようになっていくのです。
このように、20世紀のデンマークは、戦争と占領を乗り越えつつ福祉国家としての体制を確立し、国際社会での地位を高めていった時代だったのです。
1914年 第一次世界大戦の勃発
第一次世界大戦が勃発するも、デンマークは中立の立場をとる。しかし、想定外に長引く戦争でヨーロッパ全体が疲弊し、デンマークの商業も大きく落ち込んだ。戦争中、デンマークは経済的困難に直面し、国内の資源や食糧の供給が制約された。
1915年 デンマークで女性参政権が認められる
1915年、デンマークで女性参政権が認められ、女性も選挙権と被選挙権を持つようになった。この改革は、デンマークの民主主義と男女平等の推進における重要な一歩となり、社会的進展を象徴する出来事となった。
1920年 シュレースヴィヒ北部のデンマーク復帰
第一次世界大戦にドイツが敗戦したことで、シュレースヴィヒの北部がデンマークに復帰した。ヴェルサイユ条約に基づく住民投票の結果、シュレースヴィヒ北部の住民はデンマークへの復帰を選択。これにより、デンマークは失われた領土を取り戻し、国境の安定を確保した。
1940年 ナチスドイツによる占領
第二次世界大戦が勃発すると、不可侵条約を締結していたナチスドイツに国土を占領される。デンマークは1940年4月9日にドイツ軍の侵攻を受け、短期間の抵抗の後に降伏し、占領下に置かれた。デンマーク政府は、国民の安全を保つためにドイツ軍との協力政策を取ることを余儀なくされたが、国内ではレジスタンス運動が活発化し、ナチス占領に対する抵抗が続いた。この占領は、デンマークの戦時中の苦難とともに、後の独立回復と再建のための闘いを象徴する時期となった。
1945年 第二次世界大戦後の復興開始
第二次世界大戦が終結し、ドイツの占領から解放されたデンマークは、戦後の復興に取り組む。経済再建と社会の安定が最優先課題となった。
|
|
|
現代デンマーク
現代デンマークの歴史的な歩みは、第二次世界大戦後の復興から始まります。1945年のドイツ占領からの解放後、デンマークは戦後復興に取り組み、1949年にNATOに加盟して冷戦時代の西側陣営の一員となりました。1953年には憲法改正により議会制民主主義が強化され、1973年には欧州共同体(EC、現在のEU)に加盟し、欧州統合に積極的に参加しました。
経済面では、福祉国家モデルを採用し、教育、医療、福祉の充実を図りながら、高い生活水準と社会的平等を実現しました。特に再生可能エネルギー分野での先進的な取り組みは注目され、風力エネルギーの利用が進んでいます。
国際的には、環境問題や人権保護の分野でリーダーシップを発揮し、持続可能な社会の実現に向けた努力が評価されています。都市計画やデザイン分野でも高い評価を受け、コペンハーゲンは住みやすい都市ランキングで常に上位にランクインしています。
1949年 NATO加盟
デンマークは北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、冷戦時代の西側陣営の一員として安全保障体制を強化する。
1953年 憲法改正
デンマーク憲法が改正され、議会制民主主義が強化されるとともに、女性の王位継承が可能になる。これにより、民主主義とジェンダー平等が進展。
1973年 欧州共同体(EC)加盟
デンマークは欧州共同体(EC、現在の欧州連合、EU)に加盟し、経済・政治的な統合を深め、ヨーロッパとの結びつきを強化する。
1989年 ベルリンの壁崩壊
ベルリンの壁崩壊により、冷戦が終結し、デンマークは新たな国際秩序の中での役割を模索し始める。
1993年 マーストリヒト条約批准
デンマークはマーストリヒト条約を批准し、欧州連合(EU)のさらなる統合に向けた動きに参加。欧州統合が一層進展する。
2000年 ユーロ導入を否決
デンマーク国民は国民投票でユーロ導入を否決し、独自通貨クローネの使用を継続することを決定。
21世紀
21世紀のデンマークは、持続可能な社会の構築と国際的な協力強化を追求する時代です。まず、デンマークは環境政策において先駆的な役割を果たし、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。特に、風力発電の分野では世界をリードする存在であり、現在のエネルギー供給の多くが風力によって賄われているのが特徴です。2050年までに化石燃料を完全に排除する目標を掲げており、持続可能な発展を目指すその姿勢は世界的に高く評価されています。
また、21世紀初頭には移民や難民問題が大きな政治課題となりました。デンマークはヨーロッパ内での移民制限政策を強化し、特に2015年の難民危機以降、社会統合と安全保障のバランスを模索しています。これに関連して、右派政党の台頭や、移民政策を巡る議論が激化し、国内の政治風景も変化を見せています。なおかつ、こうした課題への取り組みを通じて、社会の多様性と統合のあり方についても再考が求められていますね。
さらに、国際的な協力の分野では、デンマークは欧州連合(EU)との関係を強化しつつも、独自の外交方針を維持しています。安全保障面では、NATOの一員としての役割を果たしながら、グリーンランドや北極圏での戦略的な位置付けを重視。気候変動対策においては、グローバルな枠組みの中で積極的に関与し、国際会議や条約において重要な役割を果たしているのです。
このように、21世紀のデンマークは、環境先進国としての地位を強化しつつ、移民政策や国際協力の課題に取り組み、持続可能で安定した社会の構築を目指す時代となっています。
2001年 アフガニスタン派遣
デンマークは国際連合の要請に応じ、アフガニスタンに軍を派遣。国際的な平和維持活動に積極的に関与する。
2009年 コペンハーゲン気候変動会議
コペンハーゲンで国際連合気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)が開催され、気候変動対策の重要性が強調される。
2014年 マーストリヒト条約批准の20周年
デンマークはマーストリヒト条約批准から20周年を迎え、欧州統合の進展とデンマークの役割を再評価する。
2015年 難民危機への対応
シリア内戦などにより欧州全体で難民危機が発生。デンマークも難民受け入れに対する議論が活発化し、移民政策が大きな焦点となる。
2020年 COVID-19パンデミック
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、デンマークもロックダウンや経済対策を実施。感染拡大防止と経済支援に注力する。
デンマークの歴史は、古代から現代に至るまで多様な変遷を遂げてきました。古代にはゲルマン系の部族が定住し、青銅器文化や鉄器文化が発展しました。中世にはバイキングとして知られるデーン人が活動し、10世紀にハラルド・ブルートゥース王によってキリスト教化と王国の統一が進められました。14世紀末にはカルマル同盟が成立し、北欧全域を支配する大国として君臨しました。近世には絶対王政が確立され、商業と海軍力が強化されました。19世紀には憲法改正により立憲君主制が確立され、第二次世界大戦後には復興と共にNATOや欧州連合(EU)に加盟。現代のデンマークは、福祉国家モデルと再生可能エネルギーの先進国として知られ、高い生活水準と国際的な影響力を持つ国へと成長しています。
|
|
|































