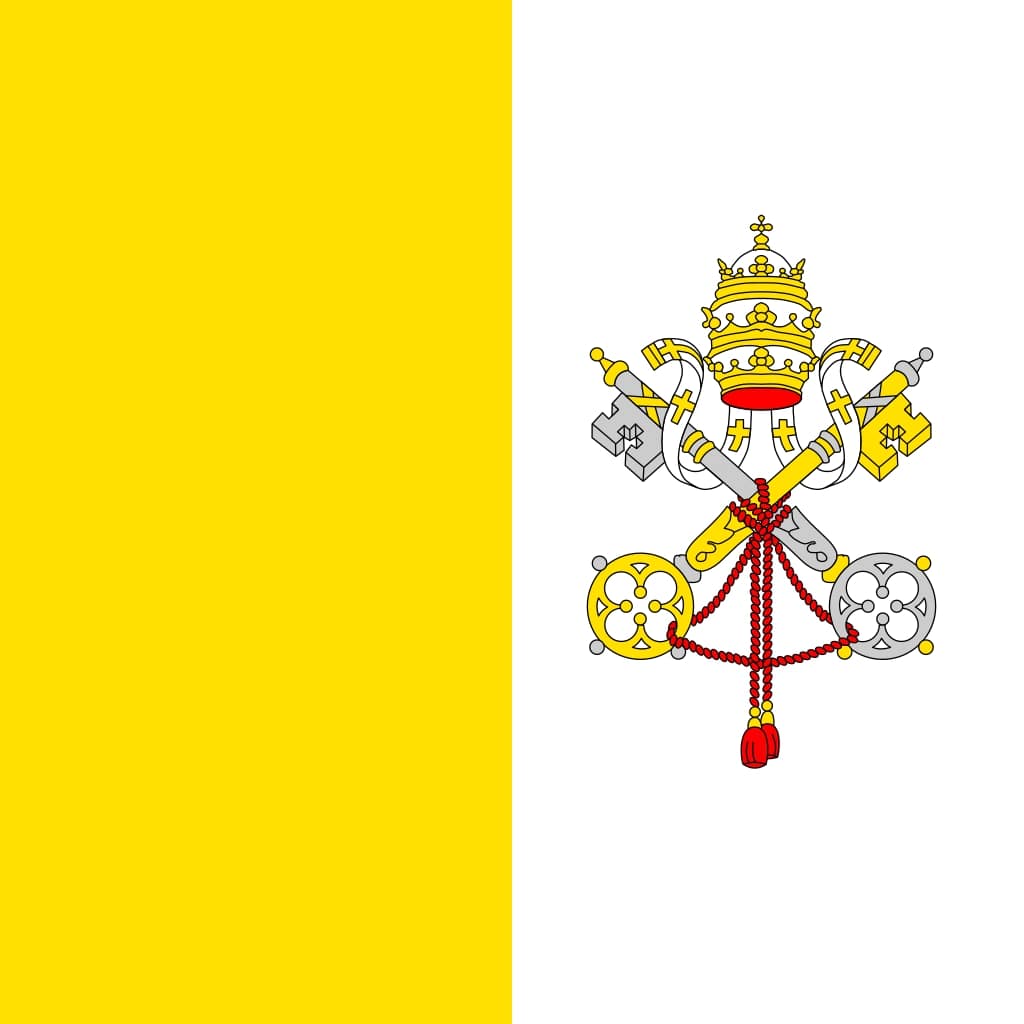ポルトガル史の流れを年表でつかもう

ポルトガルの国旗

ポルトガルの国土
| 年代 | 出来事 | 時代 |
|---|---|---|
| 前200年頃 | ローマ帝国がルシタニア地方を征服 | 古代 |
| 5世紀 | 西ゴート王国の支配下に入る | 古代末期 |
| 711年 | イスラム勢力(ムーア人)がイベリア半島に侵入 | 中世 |
| 868年 | ポルトゥカレ伯領が成立(ポルトガルの起源) | 中世 |
| 1139年 | アフォンソ1世が自らをポルトガル王と宣言 | 中世 |
| 1143年 | レオン王国がポルトガルの独立を承認 | 中世 |
| 1249年 | レコンキスタ完了(アルガルヴェ征服) | 中世 |
| 1386年 | イングランドとウィンザー条約締結(現存する最古の同盟) | 中世 |
| 1415年 | セウタ征服、海外進出の始まり | 近世 |
| 1498年 | ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開拓 | 近世 |
| 1500年 | カブラルがブラジルに到達 | 近世 |
| 1580年 | スペイン王フェリペ2世がポルトガルを併合(イベリア連合) | 近世 |
| 1640年 | 独立回復戦争勃発、ブラガンサ家による王政復活 | 近世 |
| 1755年 | リスボン大地震と大津波で壊滅的被害 | 近世 |
| 1807~1811年 | ナポレオン戦争中、フランス軍が侵攻 | 近代 |
| 1822年 | ブラジルが独立 | 近代 |
| 1910年 | 共和制宣言、ポルトガル第一共和政始まる | 近代 |
| 1926年 | 軍事クーデターで独裁体制へ移行 | 近代 |
| 1933年 | サラザールによるエスタド・ノヴォ体制開始 | 近代 |
| 1974年 | カーネーション革命により独裁体制崩壊、民主化 | 現代 |
| 1975年 | アフリカ諸植民地の独立(アンゴラ・モザンビークなど) | 現代 |
| 1986年 | EC(現EU)加盟 | 現代 |
| 1999年 | マカオを中国に返還 | 現代 |
| 2002年 | ユーロ導入 | 現代 |
| 2011年 | 財政危機によりEUとIMFの支援受け入れ | 現代 |
| 2023年 | 観光と再生可能エネルギーを柱に経済回復継続 | 現代 |
ポルトガルの歴史詳細
ポルトガル(正式名称:ポルトガル共和国)は、西ヨーロッパのイベリア半島に位置する共和制国家です。国土はイベリア半島西端の平地と大西洋上のアソーレス諸島、マデイラ諸島で構成され、気候区は地中海性気候に属しています。首都は「欧州文化首都」として知られるリスボン。
この国ではとくに農業が発達しており、中でもオリーブ、小麦の生産がさかんです。またポルトガル王国時代の遺産を背景にした観光業もこの国の基幹産業となっています。
そんなポルトガル共和国の歴史は、868年にアルフォンソ3世によって建設されたポルトゥカーレ伯領から始まるといえます。その後王国となったポルトガルは大航海時代に数多くの海外領土を得るなど繁栄を極めました。1910年に共和国化して現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなポルトガル共和国の歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。
|
|
|
古代ポルトガル
古代ポルトガルには、先住民としてルシタニア人が暮らしていました。前2世紀以降、古代ローマの進出が始まり、その同化圧力に抵抗を続けていましたが、前1世紀には、ポルトガル含めたイベリア半島全体が完全にローマの支配下におさまります。
ローマ支配下で、イベリア半島は「ルシタニア」として知られるようになり、その領域は現在のポルトガルの大部分に加えて西スペインの一部を含んでいました。ローマ化の影響で、都市が建設され、道路網が拡張され、ローマの法律、文化、言語が導入されました。経済も発展し、特にオリーブオイル、ワイン、銅、錫の生産が盛んになり、これらの商品はローマ帝国全土に輸出されました。この時代の遺跡やアーチファクトが、ローマ文明と地元文化が融合した独自の文化遺産を今に伝えています。
前5世紀
前500年頃 ポルトガル北部にケルト人が居住開始。ケルト人は、この地に独自の文化と社会構造を持ち込み、農業や金属加工技術を発展させた。彼らの定住により、ポルトガル地域はケルト文化の影響を受けた共同体が形成され、後のルシタニア人の文化的基盤が築かれた。ケルト人の影響は、後にローマ帝国による征服と同化を経て、ポルトガルの歴史と文化に深く刻み込まれることとなった。
前2世紀
前181年 第一次ケルティベリア戦争(~179年)
イベリア半島の支配を目論む共和政ローマと現地住民との戦争が起こる。この戦争は、ローマの拡張主義に対するケルト・イベリア部族の抵抗を特徴とし、特にルシタニア人やケルティベリア人が激しく抵抗した。戦争は数年間にわたり、激しい戦闘が繰り広げられたが、最終的にローマは勝利し、イベリア半島の支配を強化することに成功した。この戦争の結果、ローマ文化と法律がイベリア半島に浸透し、地域の歴史に大きな影響を与えることとなった。
前155年 ルシタニア戦争(~前139年)
イベリア半島の支配を確立したい共和政ローマと、西部ルシタニア(現ポルトガルの中北部)のルシタニア人との武力衝突ルシタニア戦争が起こる。決着はなかなかつかなかったが、ルシタニアの王がローマの差し向けた刺客に暗殺されたことにより、ルシタニア軍は瓦解していき、敗北を喫した。
前1世紀
前60年 カエサルによるルシタニア族討伐
カエサルがルシタニア族を討伐し、イベリア半島のローマ支配を強化。ルシタニア族は勇猛な戦士として知られており、ローマに対して長期間にわたる抵抗を続けていたが、カエサルの軍事戦略と圧倒的な軍事力により、最終的には制圧された。この討伐により、ローマはルシタニア地域を完全に掌握し、ローマ化が進行した。ローマの支配下で道路網や都市が整備され、地域の経済と文化が大きく発展することとなった。
前27年 ローマ属州ルシタニアの建設
ローマ皇帝アウグストゥスのもと、現在のポルトガル・スペイン西部地域を管轄するローマ属州ルシタニアが作られる。州都はエメリタ・アウグスタ(現スペインのメリダ)に置かれた。この属州は、ローマ帝国の西部の重要な拠点として発展し、経済的、軍事的な要地となった。ローマの統治下で、道路網やインフラが整備され、都市化が進行し、ローマ文化と生活様式が広がった。ルシタニアは、農業や鉱業の中心地としても重要な役割を果たし、ローマ帝国全体にとって重要な地域となった。
4世紀
4世紀末期にはローマ帝国が西ローマ帝国と東ローマ帝国(ビザンツ帝国)に分裂し、ポルトガルは西ローマ帝国の支配下に入る。
5世紀
415年 西ゴート王国の建国
西ローマ帝国の衰退にともない、イベリア半島にゲルマン系西ゴート族が流入。彼らはここに西ゴート王国を建国した。ゲルマン文化、ローマ文化、キリスト教文化が合わさった独特の文化が栄えた。
476年 西ローマ帝国の崩壊
西ローマ帝国が崩壊すると、西ゴート王国はその機に乗じて、旧西ローマ帝国領にまで勢力を広げた。西ゴート族はイベリア半島の広範囲を支配し、特に現在のポルトガルとスペインの大部分を統治するようになった。彼らはローマの行政機構を利用しつつ、新たな政治体制を築き、キリスト教の広がりを促進した。この時期、ローマ文化とゲルマン文化が融合し、地域の社会構造と文化に深い影響を与えることとなった。西ゴート王国の支配は、後のイスラム教徒の侵攻まで続いた。
|
|
|
中世ポルトガル
西ローマ帝国が崩壊すると、今度はイスラム勢力に服属しますが、12世紀半ばにアルフォンソ1世がイスラム勢力と戦い、レコンキスタ(再征服)を達成。ポルトガル王国を成立させました。
アルフォンソ1世は1143年のザモラ条約によってレオン王国から独立を認められ、これによりポルトガル王国の基盤が固まりました。彼の治世下で、ポルトガルはテージョ川以南の地域を征服し、地中海へのアクセスを確保。国境を拡張することで、国の経済的基盤も強化されました。
その後、アルフォンソ1世は文化と科学の発展にも力を入れ、多くの宗教施設の建設を推進し、ポルトガルのアイデンティティを確立する重要な役割を果たしました。このようにして中世ポルトガルは、キリスト教国としての地位を固め、その後の拡大への道を開いたのです。
6世紀
6世紀に入り、ガリアを中心に勃興したフランク王国が、イベリア半島を中心とした西ゴート王国の勢力圏を圧迫するようになった。フランク王国軍との戦闘ではことごとく敗れ、領地を次々と失っていった。また6世紀末には西ゴート王レカレド1世がカトリックへの改宗を行った。
7世紀
6世紀末の改宗以降、徐々に勢力を取り戻していき、7世紀前半には再びイベリア半島のほぼ全域の支配を確立することができた。
8世紀
711年 西ゴート王国の滅亡/アストゥリアス王国の成立
イスラム勢力がイベリア半島に侵入。グアダレーテ河畔の戦いでロデリック王が戦死したことで西ゴート王国は滅んだ。以降イベリア半島はウマイヤ朝の支配下におかれる。一部の王族はイベリア半島北部に逃れ、アストゥリアス王国を建国。キリスト教勢力によるレコンキスタ(国土回復運動)の拠点となった。
722年コバドンガの戦い
イベリア半島北西部のコバドンガ近辺の山中にて、アストゥリアス王国軍とウマイヤ朝軍が衝突。キリスト教勢力のアストゥリアス王国が勝利し、レコンキスタが一歩前進した。
9世紀
866年 ポルトゥカーレ伯領の設置
レコンキスタを目的として、現ポルトガルの北部地域にポルトゥカーレ伯領が設置される。この伯領は、キリスト教徒によるイスラム教徒からの領土奪還運動の一環として設立され、レコンキスタの重要な拠点となった。ポルトゥカーレ伯領は後にポルトガル王国の成立につながる基盤を築くこととなる。
10世紀
910年 レオン王国の成立
アストゥリアス王国は首都を軍事的要衝のレオンに遷都し、以降この国はレオン王国と呼ばれるようになる。レオン王国はレコンキスタの前線基地として、イスラム教徒からの領土奪還運動を推進し、イベリア半島北部のキリスト教勢力の中心となった。
997年 ポルトガルの奪還
レコンキスタ(国土回復運動)でポルト(ポルトガル北部の港湾都市)を奪還。ポルトガルはこの時期に再びキリスト教徒の支配下に入り、以降のレコンキスタ運動において重要な拠点となる。この奪還は、ポルトガル地域の政治的・宗教的復興の一歩となった。
12世紀
1139年 ポルトガル王国の成立
ポルトゥカーレ伯アフォンソ1世が、オーリケの戦いでイスラム勢力を破る。その後ポルトガルの王を自称したことでポルトガル王国が成立した。
1147年 リスボンの奪還
アフォンソ1世率いる十字軍がレコンキスタに乗り出し、現ポルトガルの首都リスボンを奪還した。
13世紀
1242年アルガルヴェ王国の成立
サンシュ2世により、アルガルヴェ地方(ポルトガルの最南端)にアルガルヴェ王国が建設され、ポルトガル王がアルガルヴェ王を兼ねるようになる。アルガルヴェがポルトガル支配におさまったことで、現在のポルトガルの国土が完成した。
14世紀
1348年 ペストの蔓延
ペスト(黒死病)がポルトガルを含むヨーロッパ全土に蔓延し、多くの人命が失われる。ポルトガルの人口も大幅に減少し、社会と経済に深刻な影響を与えた。農業生産は停滞し、労働力の不足が広がり、経済の回復には長い時間がかかった。この疫病の蔓延は、封建制度の崩壊と社会構造の変化を促進し、後の歴史における重要な転換点となった。
1385年アヴィス王朝の成立
アヴィス修道会長のジョアン1世がポルトガル王に即位しアヴィス王朝が創始した。この王朝は積極的な海外進出を行い、ポルトガル大航海時代を確立した。
1386年 ウィンザー条約の締結
イングランドとの間で、現存する最古の2国間同盟「ウィンザー条約」が締結される。この条約により、ポルトガルとイングランドの間に永続的な友好と相互支援が約束された。ウィンザー条約は、両国の軍事的・経済的協力を強化し、特に百年戦争におけるイングランドの対フランス戦略において重要な役割を果たした。また、この同盟はポルトガルの独立を守る上でも重要であり、後の歴史においても両国の関係を深める基盤となった。
|
|
|
近世ポルトガル
15世紀にはエンリケ航海王子の指揮のもと、バスコ・ダ・ガマやマゼランなど有能なポルトガル人航海士を支援し、新航路を開拓。スペインと共に一大海洋帝国を築き上げ、世界有数の海洋国家として繁栄を謳歌しました。しかしピークが過ぎると内政の乱れから国力は衰えていきます。
17世紀に入ると、ポルトガルはスペインとの60年に及ぶ同君連合のもとで苦境に立たされ、1640年の復古戦争で独立を回復しますが、その後も経済的な困難に直面しました。特にブラジルを中心とした植民地からの金や宝石の流入が減少し、イギリスとのメシアニック条約によって経済の自主性を失うなど、国際的な立場も弱まりました。さらに、18世紀の地震によるリスボンの大破壊は国を一層の危機に陥れ、内政の混乱と国力の衰退を招いたのです。
15世紀
1415年セウタ占拠
イスラム勢力の脅威を根絶する目的で、アフリカ大陸北岸のセウタを攻撃・占拠する。アヴィス王朝が断絶(1580年)し、スペインに支配圏が渡るまではポルトガル領として過ごした。
1427年 アゾレス諸島の発見
ポルトガル人航海者によりリスボン西方の海洋に浮かぶアゾレス諸島が発見される。紀元前にはカルタゴ人が暮らしていた島々。発見まもなくポルトガル人の植民が開始され、新大陸進出のための重要な中継路となった。
1488年 喜望峰の発見
ポルトガル人航海士のバルトロメウ・ディアスが、ヨーロッパ人として初めて喜望峰を発見。ポルトガルはこの発見を足掛かりとして、いち早くインド洋に進出し、貿易の覇権を握った。
1494年 トルデシリャス条約の締結
スペインとトルデシリャス条約を結ぶ。紛争回避を目的に、「新世界」で発見された土地を2国で分割することが決定する。
1497年 インド航路の開拓
ポルトガルの探検家バスコ・ダ・ガマがインドへの航路を発見する。その後ポルトガル人のゴア(インド西海岸の地域)への入植やインドとの貿易が開始された。
1500年 ペドロがブラジルに到達
ポルトガルの探検家ペドロ・アルヴァレス・カブラルがブラジルに到達し、ポルトガルの植民地とする。この発見により、ポルトガルは南米大陸に広大な植民地を持つこととなり、ブラジルはポルトガル帝国の重要な拠点となった。ブラジルの発見と植民地化は、ポルトガルの大航海時代の成功を象徴し、同国の経済と影響力を世界中に拡大する契機となった。
16世紀
1515年 港湾都市ホルムズの征服
ポルトガルはペルシア湾の都市ホルムズを征服し、香料交易で優位に立つ。この征服により、ポルトガルはインド洋の貿易路を支配し、アジアとヨーロッパを結ぶ重要な交易拠点を確保した。ホルムズの支配はポルトガルの海上帝国の拡大に寄与し、香辛料やその他の貴重品の貿易で莫大な利益を得ることとなった。この戦略的な勝利により、ポルトガルは16世紀の世界貿易における覇権を握ることができた。
1557年 ポルトガル領マカオの成立
明から租借したマカオにポルトガル人居住区が設立される。その後、中国や日本との貿易(主に生糸、金、銀など)で多大な利益をあげた。
1572年 ウズ・ルジアダス出版
大航海時代の栄光が書かれた叙事詩『ウズ・ルジアダス』が出版される。この叙事詩は、ポルトガルの偉大な詩人ルイス・デ・カモンイスによって書かれ、ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路発見を中心に、ポルトガルの探検と航海の英雄的な業績を描いている。『ウズ・ルジアダス』はポルトガル文学の最高峰とされ、国民的誇りの象徴となった。この作品はポルトガルの歴史と文化に深い影響を与え、ポルトガルの大航海時代の栄光を後世に伝える重要な文学作品となった。
1580年 スペインに併合
スペイン・ハプスブルク家のフェリペ2世がポルトガル王位を継承し、ポルトガルがスペインに併合される。
17世紀
海上覇権を確立し、アジアにおける貿易利権を独占していたポルトガルおよびスペインだが、17世紀になると、オランダやイギリスといった新興勢力が競合してくるようになった。
1640年 ポルトガル王政復古戦争の勃発(~68年)
リスボンで起こったポルトガル人貴族による反スペインの革命運動から、ポルトガル王国とスペイン帝国の戦争に発展。ポルトガルの自治を縮小し、中央集権化をはかるスペインへの反発がきっかけとなった。
1668年 スペイン王国からの自治独立
ポルトガル王政復古戦争の結果、ポルトガルの勝利となり、60年に渡って続いたスペインとの同君連合が解消。スペインにポルトガルの独立を認めさせた。
18世紀
18世紀からは南米ブラジルの植民活動に力を入れるようになり、とくにブラジルにおける金の産出はポルトガルに莫大な利益を生んだ。
1701年 スペイン継承戦争の勃発(~13年)
スペイン国王の死去にともない、遺言に従いスペイン王位を継ごうとするフランスと、フランスの強大化を恐れ、それを阻止したいイギリス・オランダ・オーストリアとの間で、スペイン継承戦争が勃発した。ポルトガルは対仏連合に味方し、フランス・スペインと争った。ユトレヒト条約とラシュタット条約の締結により講和。
1703年メシュエン条約
ポルトガルとイギリスの間で、イギリスが毛織物を輸出する代わりに、ポルトガルから輸入するワインの関税を引き下げるという通商条約が結ばれる。この条約をきっかけに、ポルトガル経済はイギリスに依存していった。
1755年 リスボン震災
港湾都市リスボンに壊滅的な被害をもたらしたリスボン大震災が発生し、津波によるものも含め6万2000人が犠牲になった。多くの歴史ある建築物や美術品もこの震災で失われた
リスボン震災は「国家」として、はじめてその対応や復興に責任を負ったことから、ヨーロッパ社会に科学や技術の面で転機をもたらした「近代的災害」ともいわれています。この震災を教訓にしたリスボンは世界初の耐震都市になりました。
1788 ミナスの陰謀
ポルトガル植民地ブラジル・ミナスジェライス州で、金の産出量減に対するポルトガル王室の課税強化をきっかけとする反乱計画「ミナスの陰謀」が露呈。反乱計画参加者は主にエリート層が占めていた。アメリカの独立に刺激を受けて起こったもので、独立運動の先駆けといわれている。
1789年 フランス革命
フランス革命が勃発し、ヨーロッパ全土に大きな政治的変動をもたらす。この革命はポルトガルにも影響を及ぼし、フランス革命の理念がポルトガル国内に広まり、社会的・政治的な動揺を引き起こした。特に貴族階級と市民階級の対立が激化し、後の政治改革や自由主義運動の基盤を形成することとなった。ポルトガルは革命の波及を警戒し、国内の安定を保つために多くの対策を講じたが、19世紀初頭のナポレオン戦争においても、フランスの影響下に置かれることとなった。
1798年 バイーアの陰謀
ポルトガルのブラジル植民地バイーアにて、仕立て屋をはじめとした平民、さらには奴隷や自由身分の黒人まで巻き込んだ反乱計画が露呈。フランス革命に刺激を受けた人々の支持を受けたとみられている。
|
|
|
近代ポルトガル
19世紀になるとポルトガル王国最大の植民地ブラジルが独立し、20世紀初頭には共和革命で王制は崩壊し共和政に移行します(ポルトガル第一共和政)。第一次世界大戦が終結すると財政悪化から共和国政府への不満が高まり、軍事クーデターにより共和制は崩壊。軍事独裁政権が誕生してしまいます。その後のポルトガルでは、ファシズム憲法のもと全体主義体制が確立され、以後「エスタド・ノヴォ」と称される、40年にもおよぶヨーロッパ最長の独裁政権が続いたのです。
このエスタド・ノヴォ政権のもとで、アントニオ・デ・オリヴェイラ・サラザールが長期間にわたり政権を掌握しました。サラザールは厳格な検閲と秘密警察を用いた厳しい抑圧政策を行い、反対勢力を徹底的に排除しました。また、彼の経済政策は保護主義に基づいており、ポルトガル経済はある程度の安定を見せたものの、多くの市民は依然として貧困状態にありました。
1974年、カーネーション革命が起こり、この革命により無血のクーデターが成功し、民主化への道が開かれました。この政変によって長きにわたる独裁政権は終わりを迎え、ポルトガルは新たな民主的体制へと移行したのです。
19世紀
1807年 ナポレオンのポルトガル征服
ヨーロッパ征服戦争(ナポレオン戦争)を開始したナポレオン・ボナパルトが、敵対するイギリスに加担するポルトガルに侵攻を開始。ポルトガル王室はブラジルに逃亡を余儀なくされ、その間ポルトガルの首都はリオデジャネイロに遷都した。
1808年 半島戦争の勃発(~14年)
イベリア半島にて、スペイン、ポルトガルがナポレオン支配からの解放を掲げ戦争を起こす。結果的にフランス軍を撤退させることに成功し・ナポレオン凋落の一因となるも、戦争終結後ポルトガルの国土は荒廃し、長期間の政治的混乱につながってしまった。
1815年 ポルトガル・ブラジル連合王国の成立
ナポレオンによるポルトガル征服をうけ、ポルトガル王室は植民地のブラジル・リオデジャネイロに避難。以降はブラジル公国をポルトガルと同格の王国とみなし、「ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国」としてポルトガル・ブラジルによる同君連合を結成した。
1820年 1820年自由主義革命の勃発(~26年)
北部ポルトでの蜂起から始まり、ポルトガル全土で革命運動が起こった。スペイン立憲革命に刺激を受けて起こったもの。この運動の中で、自由主義的な憲法が公布され、ポルトガルにおける立憲時代が始まった。
1822年 ブラジルがポルトガルから独立
ブラジルがポルトガルとの同君連合を解消し、ブラジル帝国として独立した。ポルトガル皇太子ペドロ1世がブラジル皇帝として即位し、ブラジル独立の象徴となった。この独立はポルトガルにとって大きな経済的・政治的打撃となり、ポルトガル帝国の縮小を意味した。しかし、独立後もブラジルとポルトガルの間には文化的・経済的なつながりが続き、両国の関係は友好的に保たれた。ブラジルの独立は、南アメリカ全土での独立運動を刺激し、他の植民地にも大きな影響を与えた。
1828年 ポルトガル内戦の勃発
自由主義と絶対王政の対立が深まり、自由主義者のジョアン6世没後、ポルトガル王国の王位継承をめぐり内戦に発展した。
1834年 マリア2世がポルトガル王に即位
自由主義派の勝利をもってポルトガル内戦が終結。ブラジル皇帝ペドロの娘、マリア2世がポルトガル王位を継承した
20世紀前半
1910年 ポルトガル第一共和政の成立
ポルトガル王室の政策に対する不満や国内の共和主義者が勢力を拡大する中、リスボンで1910年革命が勃発し、王党派が打倒される。ブラガンサ王朝は滅び、ポルトガル第一共和政が成立した。
1911年 ポルトガル共和国憲法の採択
ポルトガル共和国憲法が採択され、女性参政権が認められる。この憲法は、1910年の革命によって君主制が廃止され、ポルトガルが共和国となった後に制定された。新憲法は民主的な政治体制を確立し、市民の権利と自由を保障した。女性参政権の導入は、ポルトガルにおける男女平等の推進と社会改革の一環として重要な進展であり、女性の政治参加が制度的に認められるようになった。これにより、ポルトガルは近代的な民主国家としての歩みを進めることとなった。
1914年 第一次世界大戦の勃発
サラエボ事件をきっかけとして第一次世界大戦が開始される。ポルトガルは当初中立を維持したものの、1916年に対独宣戦を行ない連合国側として参戦した。
1926年 軍事政権の樹立
第一共和政政府の不安定な政権運営に業を煮やし、ポルトガル軍がクーデターで政権を奪い、軍事政権を樹立させた。以降ポルトガルでは74年のカーネーション革命まで、軍事独裁体制が続くこととなる。
1933年 エスタド・ノヴォ体制の開始
エスタド・ノヴォ憲法が採択され、ストライキや反政府運動の禁止、言論の自由の制限など独裁が強化された。軍事独裁といえど表向きの国名は「ポルトガル共和国」であり、この憲法の採択をもって第二共和政が成立したともいえる。
1939年 第二次世界大戦の勃発
ドイツのポーランド侵攻を発端として第二次世界大戦が勃発。ポルトガルは当初ドイツ・イタリアのファシズム政権に親和的だったが、枢軸国の戦局が劣勢に傾くと、連合国寄りの姿勢にシフトした。
20世紀後半
1949年 北大西洋条約機構(NATO)に加盟
ポルトガルは北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、西側諸国との軍事的連携を強化した。この加盟により、ポルトガルは冷戦時代の西側防衛体制の一翼を担い、国際的な安全保障の枠組みに組み込まれた。
1955年 国際連合に加盟
ポルトガルは国際連合に加盟し、国際社会の一員として正式に認められる。これにより、ポルトガルは国際的な協力と平和維持活動に参加し、外交活動を活発に展開するようになった。
1960年 欧州自由貿易連合に加盟
ポルトガルは欧州自由貿易連合(EFTA)に加盟し、貿易と経済の自由化を進める。これにより、ポルトガルの経済は欧州市場と密接に結びつき、輸出入の拡大と経済成長が促進された。欧州との経済的な結びつきは、ポルトガルの近代化と経済発展に大きく寄与することとなった。
1961年 ポルトガル植民地ゴアがインドに併合
インド軍がポルトガルが植民地として領有していたゴア(インド西海岸に位置)に進軍し、ポルトガル勢力をインドから完全に追い出した。ゴアはポルトガル海上帝国時代、ポルトガルのアジアにおける重要な拠点とされていた。
1964年モザンビーク独立戦争(~75年)
ポルトガル植民地のモザンビークにて、モザンビーク解放戦線がポルトガル支配に対する反乱を起こし、モザンビーク独立戦争が開始された。
|
|
|
現代ポルトガル
現代ポルトガルは、1974年のカーネーション革命後に確立された民主的体制が特徴です。EU加盟国として経済の近代化を進め、観光業が重要な役割を担っています。経済危機からの回復や社会政策の進展にも取り組んでおり、LGBTQ+ の権利拡大など、包摂的な社会を形成しています。国際的には、NATO加盟やポルトガル語圏諸国コミュニティ(CPLP)を通じて積極的な外交を展開しているのが現代ポルトガルの顕著な特徴です。
1974年 カーネーション革命/ポルトガル第三共和政の成立
1926年以来続いていた軍事独裁制が、ほぼ無血の革命により倒れる。カーネーションが革命運動のシンボルに使われたため「カーネーション革命」と呼ばれる。新政府のもと民主制に移行し、第三共和政が開始され、現在にいたる
1975年 モザンビークの独立
前年にカーネーション革命でポルトガルの軍事独裁政権が倒れた結果、新政府は植民地戦争の停戦を宣言。モザンビークの独立を承認した。
1986年 EU加盟
1986年、ポルトガルは欧州経済共同体(EEC)、後の欧州連合(EU)に加盟した。この加盟はポルトガル経済に大きな変革をもたらし、多くの構造改革が推進された。EUからの資金援助により、インフラの近代化や教育、公衆衛生の向上が図られ、国全体の経済発展に寄与した。
1999年 欧州単一通貨ユーロの導入/ポルトガル領マカオ返還
1999年には二つの重要な出来事があった。一つ目は、ポルトガルがユーロ圏に参加し、ユーロを公式通貨として導入したことだ。これにより、経済の安定と成長が促進され、国際貿易が容易になった。二つ目は、ポルトガルが長年統治していたマカオを中国に返還したことだ。この返還は、ポルトガルと中国間の協定に基づき平和的に行われ、ポルトガルの海外領土時代の終焉を象徴した。
21世紀
2001年 EU議長国
2001年、ポルトガルは欧州連合(EU)議長国を務めた。この期間中、ポルトガルは欧州各国との協調を強化し、経済的および政治的な取り組みにおいて重要な役割を果たした。
2002年ユーロ通貨の導入
ポルトガルは2002年に紙幣および硬貨としてユーロを導入した。これはユーロ圏内での経済統合を一層深めるものであり、経済の透明性を高め、安定した貨幣政策を推進することに貢献した。ユーロの導入は、国内外での取引の便利さを向上させ、長期的な経済的安定に寄与している。
2004年 UEFAヨーロッパ選手権開催
2004年、ポルトガルはUEFAヨーロッパ選手権の開催国となり、欧州各国からサッカーファンが集まった。大会はポルトガル全土で盛り上がりを見せ、国際的な注目を集めることに成功した。
2005年 アナネル・カバコ・シルバ大統領就任
2005年、アナネル・カバコ・シルバがポルトガル共和国の大統領に就任した。彼のリーダーシップのもとで、ポルトガルは経済安定と国際的な地位向上を目指して政策が進められた。
2008年 金融危機の影響
2008年の世界的な金融危機はポルトガル経済に深刻な影響を与えた。経済成長が停滞し、失業率が急上昇。政府は緊急の財政対策を講じることを余儀なくされた。
2011年 EU・IMFからの金融支援
2011年、ポルトガルは財政危機に直面し、EUと国際通貨基金(IMF)から金融支援を受けることになった。この支援により、ポルトガルは厳しい財政緊縮策を実施し、経済の再建に努めた。
2014年 救済プログラム終了
2014年、ポルトガルはEU、ECB、IMFによる救済プログラムを終了した。この終了はポルトガルが一定の経済回復を遂げたことを示し、市場からの信頼回復に繋がった。
2016年 マルセロ・レベロ・デ・ソウザ大統領就任/UEFAヨーロッパ選手権優勝
2016年、マルセロ・レベロ・デ・ソウザが大統領に就任。同年、ポルトガル国家サッカーチームはUEFAヨーロッパ選手権で初優勝を果たし、国内外で大きな祝賀が行われた。
2017年 中部森林火災
2017年、ポルトガル中部で大規模な森林火災が発生し、多大な被害が出た。この災害は国内の緊急対応システムの見直しと防災体制の強化を迫ることとなった。
2019年 アントニオ・コスタ首相再選
2019年、アントニオ・コスタが再選され、彼のリーダーシップの下、経済成長と社会福祉の改善に向けた政策が継続された。同年、新型コロナウイルスが世界に拡散し始める。
古代ポルトガルは、ルシタニア人などの先住民族が居住しており、後にローマ帝国の一部となりました。中世にはレコンキスタを経て、アフォンソ1世によって独立国ポルトガル王国が成立しました。15世紀の大航海時代には、海外領土を拡大し、一大海洋帝国を築きましたが、19世紀にブラジルの独立などで衰退しました。20世紀には独裁政権が倒れ、1974年のカーネーション革命で民主化が進みました。1986年にはEUに加盟し、近年は経済危機の克服と復興に向けて努力しています。現代ポルトガルは、EU内での経済的・文化的な役割を担いながら、国際社会での積極的な関与を続けています。
|
|
|