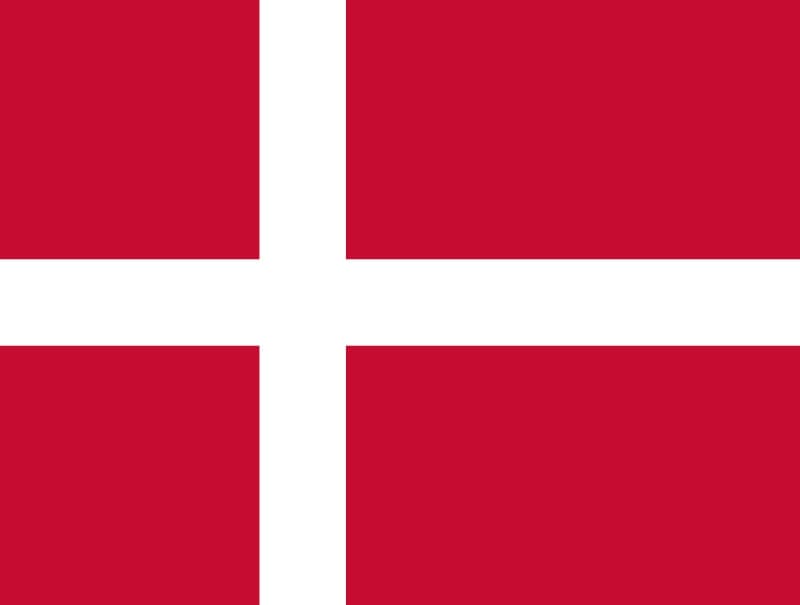ノルウェー史の流れを年表でつかもう

ノルウェーの国旗

ノルウェーの国土
| 年代 | 出来事 | 時代 |
|---|---|---|
| 8~11世紀 | ノース人(ヴァイキング)による海洋遠征と定住(イングランド・アイスランドなど) | 中世 |
| 872年 | ハーラル美髪王がノルウェー統一(ハフルスフィヨルドの戦い) | 中世 |
| 995年 | オーラヴ1世の治世、キリスト教化が進む | 中世 |
| 1030年 | 聖オーラヴ殉教、ノルウェーの守護聖人とされる | 中世 |
| 1319年 | スウェーデンと同君連合を形成 | 中世 |
| 1380年 | デンマーク王と同君連合成立(デンマーク主導) | 中世 |
| 1397年 | カルマル同盟結成(デンマーク・ノルウェー・スウェーデン) | 中世末期 |
| 1523年 | スウェーデンが同盟離脱、デンマークとの同君連合体制が続く | 近世 |
| 1814年 | キール条約でデンマークからスウェーデンへ割譲、独自憲法を制定 | 近代 |
| 1905年 | 国民投票によりスウェーデンとの連合解消、完全独立 | 近代 |
| 1940~1945年 | ナチス・ドイツに占領され、亡命政府がロンドンに成立 | 近代 |
| 1949年 | NATO創設メンバーとして加盟 | 現代 |
| 1969年 | 北海油田発見、エネルギー大国へ | 現代 |
| 1972・1994年 | EU加盟を国民投票で否決 | 現代 |
| 2001年 | ノルウェー政府年金基金(オイルファンド)拡大し世界最大規模に | 現代 |
| 2023年 | 再生可能エネルギー・福祉国家として高い国際評価を維持 | 現代 |
ノルウェーの歴史詳細
ノルウェー(正式名称:ノルウェー王国)は、北ヨーロッパのノルウェー海沿いおよび北海沿い、スカンジナビア半島の西部 に位置する 立憲君主制国家です。国土は 南北に細長く広がったスカンジナビア半島西部、およびバレンツ海上にあるスヴァールバル諸島で構成され、気候区は大部分が亜寒帯湿潤気候に属しています。首都はバルト海と北海の水陸交通を結ぶ港湾都市として知られるオスロ。
この国ではとくに 電力多消費産業が発達しており、中でもシリコン、アルミニウム、化学肥料などの生産がさかんです。また豊富な天然資源 を背景にしたガス・石油産業もこの国の基幹産業となっています。
そんな ノルウェー王国の歴史は、9世紀末にハーラル1世に建設されたスカンジナビア沿岸部の部族統一から始まるといえます。ノルウェー王国は14世紀末にはカルマル同盟のもとデンマークの支配下となります。19世紀に結ばれたキール条約によって今度はスウェーデンの支配下に収まるも、20世紀初頭には同君連合の解消を宣言。スウェーデンから独立を果たし現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなノルウェー王国の歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。
|
|
|
古代ノルウェー
ノルウェーには、紀元前10,000年頃の氷河期後に最初の人々が住み着いたとされています。これらの先住民は狩猟採集民で、主に沿岸地域で生活していました。鉄器時代以降はゲルマン系の部族が、独自の文化と社会構造を持ちつつ、農業・漁業を中心に生活し、ローマなど周辺地域との交易も行っていました。
前4世紀
北ゲルマン系のノルマン人が、現在のノルウェーの地に定着し始めます。彼らは農業や漁業を基盤とした社会を築き、寒冷な気候に適応しながら生活を送りました。ノルマン人の定住は、ノルウェーの文化や言語の形成に大きな影響を与え、後のバイキング時代に繋がる基盤を築いたのです。この時期からノルウェーの土地は徐々に開拓され、独自の文化と社会構造が発展していったといえます。
|
|
|
中世ノルウェー
8世紀頃のノルウェーでは、バイキングと呼ばれる海洋民族が活発に活動していました。9世紀末になると、ユングリング家のハーラル1世(別名:美髪王)が、ノルウェーを統一支配し、最初のノルウェー王に即位したといわれています。ノルウェーはその後大西洋へも勢力を広げ、13世紀にはアイスランドまで支配下に治めるほど優勢を振るうようになります。
ノルウェーはさらにグリーンランドやフェロー諸島にも進出し、北大西洋に広大な領土を築きました。この時期、ノルウェーは商業と交易の中心地としても繁栄し、特にハンザ同盟との貿易関係が重要な役割を果たしました。しかし、14世紀には黒死病の影響で人口が激減し、経済が停滞しました。さらに1397年にはカルマル同盟の成立により、デンマークとスウェーデンとともに同盟国となり、独立性が徐々に失われていきました。
8世紀
今世紀のノルウェーは、ヴァイキング時代の幕開けとされる時期であり、社会的・経済的な変化が急速に進行していました。
8世紀頃、ノルウェーの沿岸地域では、農業や漁業が主な生活手段でしたが、人口の増加や土地不足が深刻化し、外部への進出を余儀なくされました。この状況下で遠征や交易、略奪を通じて新しい土地や富を求め始めたのが、いわゆる「ヴァイキング活動」の始まりです。
バイキングはバルト海沿岸、ブリテン諸島、さらにはフランスやアイスランド、グリーンランドにまで進出し、その軍事力と航海技術で広範な地域に影響を与えました。8世紀末に、ノルウェー人バイキングがイギリスのリンディスファーン修道院を襲撃した事件は有名です。
この時代のノルウェーは、部族社会が中心であり、統一国家はまだ形成されていませんでしたが、バイキング活動を通じて、ノルウェーの外部との繋がりが強まり、後の統一に向けた基盤が築かれていくことになるのです。
9世紀
9世紀のノルウェーは、ヴァイキング時代の真っ只中にあり、海外遠征と内部統合の進展に特徴づけられます。この時期、ノルウェーのヴァイキングたちは、イギリス諸島やフランス、アイルランド、さらにはアイスランドやグリーンランドまで広範囲に渡って航海し、交易や略奪を行いました。
また、9世紀はノルウェー内部でも重要な変化の時期でした。ノルウェーの地方豪族たちは、互いに競い合いながら権力を強化していき、その中からハーラル美髪王(ハーラル1世)が登場しました。彼は、880年代から890年代にかけてノルウェー統一を推し進め、最終的には多くの地方領主を従え、ノルウェー初の統一王国を築くことに成功しています。ハーラル美髪王の統一事業は、後のノルウェー王国の基盤を築くものとなったのです。
9世紀のノルウェーは、外部への積極的な進出と内部の統一が進み、ヴァイキング時代の絶頂期に位置付けられる時代です。この時期にノルウェーが築いた影響力と統一の動きは、後のスカンジナビア全体に広がるヴァイキングの遺産として重要な意義を持つことは知っておきましょう!
10世紀
10世紀のノルウェーは、ヴァイキング時代の後半にあたり、統一とキリスト教化が進展する重要な時代でした。
ノルウェー国内では、9世紀末にハーラル美髪王によって統一が進められたものの、10世紀にかけて王権が低下、地方豪族たちの間で内紛が続くようになりました。そして次はハーラル美髪王の子孫であるハーラル灰衣王やハーコン善王といった王たちが現れ、再びノルウェー統一を推し進めるようになるのです。
特にハーコン善王(ハーコン1世、在位:935年-961年)は、キリスト教による宗教統一を試みましたが、地方豪族たちの抵抗にあい、その定着は一時的なものでした。しかし、この試みはノルウェーキリスト教化の基礎を築き、その後の国教化に繋がりました。
10世紀のノルウェーは、国内の統一と宗教的変革が進みつつも、依然としてヴァイキングとしての影響力を保持し、外部世界との交流を続けた時代でした。この時期の動きが、後の中世ノルウェー王国の形成に重要な役割を果たしたのです。
911年 ノルマンディー公国の成立
フランスに侵入したノルマン人により、ノルマンディー公国が建国される。その後ノルマンディー公はイングランドを征服し、ノルマン朝を創始する。
995年 オーラヴ・トリュッグヴァソンの即位
オーラヴ・トリュッグヴァソンがノルウェー王オーラヴ1世として即位。ノルウェーのキリスト教化に尽力。異教の弾圧を行い、キリスト教を王権の土台にした統治を行った。
1000年 スヴォルドの海戦
ノルウェー王オーラヴの軍と、デンマーク、スウェーデンなどの連合軍との間で海戦が行われた。オーラヴはこの戦いの中で死に、ノルウェー軍は全滅した。
11世紀
11世紀のノルウェーは、国内のキリスト教化と国家統一が完成する重要な時代でした。
オーラヴ2世(オーラヴ聖王、在位:1015年-1028年)の時代には、キリスト教がノルウェー全土に広まりました。オーラヴはキリスト教を国教とし、異教の慣習を排除、ノルウェーをキリスト教国家へと変革したのです。彼はその後デンマーク王クヌートによって追放されますが、スティクレスタッドの戦い(1030年)で殉教し、「聖人」として崇められるようになりました。オーラヴの死はノルウェーのキリスト教化を決定的なものとし、ノルウェーの宗教的および政治的アイデンティティに大きな影響を与えたのです。
政治的統一を推し進めたのはハーラル3世(在位:1046年-1066年)。ヴァイキング時代の最後の王として知られ、東ローマ帝国での傭兵経験や遠征を通じて名声を得た人物です。治世中、ノルウェーをスカンジナビア全体に影響力を持つ強力な王国に押し上げました。
しかしその一方で、ハーラル3世がスタンフォード・ブリッジの戦い(1066年)でイングランドに侵攻、敗死したことで、ノルウェーのヴァイキング時代は事実上の終焉を迎えました。
このように11世紀は、ノルウェーがヴァイキングとしての影響力を失い、キリスト教国家としての確立に向けて大きな転換を遂げた時代だったのです。
1028年 デンマークに併合
王家の権力闘争でノルウェーは衰退していき、デンマークの北海帝国に併合される。デンマーク王クヌート大王がノルウェーを征服し、その統治下に置いた。この併合により、ノルウェーはデンマーク王国の一部として統治され、北欧全体の政治的・経済的な統合が進んだ。クヌート大王の治世は北海帝国の最盛期を迎え、デンマーク、ノルウェー、イングランドを含む広大な領域を支配することとなった。
1030年 スティクレスタドの戦い
デンマーク艦隊に敗れスウェーデンに逃れていたオーラヴ2世だが、その後ノルウェーに帰還しようとして起こったスティクレスタドの戦いで地元の豪族に敗れ死去。
1046年 ハーラル3世の即位
オーラブ2世の異父弟ハーラル3世がノルウェー王に即位。はじめはマグヌス1世と共同統治だったが、47年にマグヌスが戦死したことで単独のノルウェー王となった。敵に対する容赦のない扱いから「苛政王」の通り名をもつ。
12世紀
12世紀のノルウェーは、王権の強化と教会の影響力が拡大した時代であり、国内の統一とキリスト教社会の確立が進みました。この時期、ノルウェー王国はハーラル・ギッレやスヴェレ・シグルツソンといった王たちの治世を経て、内紛や権力闘争を繰り返しながらも、中央集権化が進められていったのです。
ハーラル・ギッレ(在位:1130年-1136年)の死後、ノルウェーでは内戦が勃発し、王位を巡る争いが続きました。この内戦は、ノルウェー全土を巻き込んだ混乱を招きましたが、最終的にスヴェレ・シグルツソン(在位:1177年-1202年)が勝利を収め、王権を確立しました。スヴェレは、教会との対立を乗り越え、王権の強化を図りましたが、彼の治世は激しい内戦と教会との権力闘争が特徴的でした。スヴェレの死後、ノルウェーは一時的に安定しましたが、12世紀全体を通じて、王位継承を巡る争いが続き、国家統一に課題が残る結果になりました。
その一方、12世紀を通して、キリスト教がさらに深くノルウェー社会に浸透し、教会の権威が増大。多くの教会や修道院が建設され、ノルウェーの宗教的生活が整備されたことは重要です。
12世紀のノルウェーは、王権の確立とキリスト教社会の構築が進んだ一方で、内戦や権力闘争が続いた動乱の時代であり、後の安定した統治に向けた基礎が築かれた時期といえます。
13世紀
13世紀のノルウェーは、王権の強化と国家統一の達成が進んだ時代であり、政治的安定が徐々に実現されました。特にこの時期には、内戦が続いていた12世紀からの混乱が収束し、ノルウェー王国の統一が確立されていったのです。
13世紀初頭、内戦の余波がまだ残る中で、ハーコン4世(ハーコン老人、在位:1217年-1263年)が王位に就きました。彼の治世は、ノルウェーの安定化と王権の確立を推進するものでした。ハーコン4世は、王国を再統一し、中央集権化を進める一方で、法律を整備、国内の秩序を強化したのです。また、彼の外交政策により、ノルウェーの影響力は北欧全域に拡大し、スコットランドやアイスランドとの関係も強化されました。
ハーコン4世の治世では、教会との関係が緊張することもありましたが、最終的には教会と協力して、法的・行政的制度の整備が進められました。13世紀半ばには、国法が編纂され、法治国家としての基盤が築かれています。この時期、教会の権威も増大し、修道院の建設が進み、キリスト教社会のさらなる強化が図られたことも重要です。
13世紀のノルウェーは、ハーコン4世の下で王権の強化と国家の統一が進み、法的制度と教会との関係が整備された時代であり、後の中世ノルウェー王国の繁栄に向けた基礎が築かれた時期といえます。
1217年 ホーコン4世の即位
スベッリ・シグルソンの孫ホーコン4世(在位1217年~1263年)が即位。旧貴族の撤廃、法慣習の成文化、父の代から続いていた内紛を収め、さらに領土も拡大するなど数々の成果をあげ、その治世でノルウェーは最盛期を迎えた。
1241年 アイスランドのスノッリ・ストゥルルソン暗殺
アイスランドの指導者スノッリ・ストゥルルソンが暗殺される。この暗殺はアイスランドを支配下に置こうとするホーコン4世の差し金。
1247年 ホーコン4世の戴冠
ローマ教皇使節団がノルウェーに訪れ、ホーコン4世は王冠を授けられる。この戴冠式は、ノルウェーがキリスト教世界の一員として認められた象徴的な出来事であり、ホーコン4世の治世の正統性を強化した。彼の治世はノルウェーの中世における黄金時代とされ、国家の統一と中央集権化が進み、法制度や行政の改革が行われた。また、彼の外交政策によりノルウェーの国際的な地位も向上し、貿易や文化交流が活発化した。この時期、ノルウェーは経済的にも繁栄し、国内の安定と発展が図られた。
1250年 ハンザ同盟と通商条約を締結
北ドイツ諸都市による同盟ハンザ同盟との通商条約を締結する。この同盟はノルウェーに繁栄をもたらしたが、同時にドイツに経済的主導権を握られることにもなった。
14世紀
14世紀のノルウェーは、王権の衰退と黒死病の影響を受けた時代であり、社会的・経済的な困難が増大しました。この時期、ノルウェー王国は統治の安定が難しくなり、特にペストの大流行が人口と経済に甚大な影響を与えたのです。
14世紀後半、ノルウェーはデンマークとスウェーデンとの間で結ばれたカルマル同盟(1397年)に加わり、マルグレーテ1世がデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの統治者となりました。この同盟により、ノルウェーの独立性は次第に弱まり、政治的にデンマークに従属する立場となってしまいます。同盟下でのノルウェーは、他の北欧諸国に比べて影響力を失い、王権もデンマークの支配に依存するようになるのです。
1349年にヨーロッパ全土に広がった黒死病(ペスト)がノルウェーにも襲来し、人口の大部分が死亡しました。労働力の不足により農村社会に甚大な損害を与え、経済活動が停滞。土地の所有構造や社会階層も大きく変化しました。この影響は、ノルウェー社会の復興を困難にし、国家の統一と安定をより困難なものにしてしまいました。
14世紀のノルウェーは、王権の弱体化と黒死病の打撃を受けた時代であり、カルマル同盟による統合とデンマークへの従属が進行した結果、政治的・社会的に厳しい状況に置かれた時期といえます。
1397年 カルマル同盟の結成
デンマーク国王を中心とした、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの3国による同君連合カルマル同盟が結成される。ノルウェーは再びデンマークの強力な支配を受けることとなる。
|
|
|
近世ノルウェー
中世時代に繁栄を築いたノルウェーですが、同じ北欧国家のデンマークの伸張も目を見張るものでした。中世末期になるとノルウェーは徐々にその影響力に押されるようになり、デンマークを盟主としたカルマル同盟へ加盟。ノルウェーはスウェーデンと共にデンマークの従属国としての近世に突入していくことになります。スウェーデンは16世紀にデンマーク支配を離脱することができましたが、国力が不足していたノルウェーは、デンマーク保護領としての立場に甘んじる他ありませんでした。
その結果、ノルウェーはデンマークの政治的影響下で統治されることとなり、特に文化、法律、行政などの分野でデンマーク化が進行しました。しかし、19世紀初頭のナポレオン戦争の後、1814年のキール条約によりノルウェーはデンマークからスウェーデンに割譲され、新たな統治下での歴史が始まります。
15世紀
15世紀のノルウェーは、デンマーク支配の強化とノルウェー王国の独立性の喪失が進んだ時代であり、カルマル同盟の下でノルウェーの地位が大きく変化しました。この時期、ノルウェーはデンマークの影響を強く受け、王権と独立性が次第に弱まっていったのです。
15世紀を通じて、カルマル同盟の下でノルウェーはデンマークとスウェーデンと共に統治されましたが、特にデンマークの影響力が強まりました。ノルウェーの独立した王権は形骸化し、政治的にデンマークに従属する立場へと変わっていったのです。この過程で、ノルウェーは他の北欧諸国に比べて政治的・経済的な影響力を失い、デンマークの統治に依存する状況が進行しました。
黒死病の影響が14世紀から続き、15世紀のノルウェー社会は依然として経済的な困難に直面していました。人口の減少により農業や漁業が衰退し、特に地方の農村部での経済活動が停滞。また、都市部では商業活動が縮小し、ノルウェーの経済はますますデンマークとの貿易に依存するようになりました。こうした状況は、ノルウェーの社会構造を変化させ、さらなる中央集権化を促進したのです。
15世紀のノルウェーは、デンマークの支配が強化され、独立性が喪失していった時代であり、経済的困難と社会変動の中で、ノルウェー王国が政治的に厳しい状況に置かれた時期といえます。
16世紀
16世紀のノルウェーは、宗教改革とデンマーク支配の強化が進んだ時代であり、国内の宗教的・政治的な変化が大きく影響しました。この時期、ノルウェーはデンマークとの関係がさらに密接になり、カトリックからルター派への宗教改革が進行したのです。
16世紀前半、ノルウェーは依然としてカトリック教会の影響を受けていましたが、デンマーク王クリスチャン3世が宗教改革を進める中で、ノルウェーでもルター派への改宗が推進されました。1536年、デンマークの宗教改革により、ノルウェーもルター派が国教となり、カトリック教会の権威は大幅に縮小。教会の財産は没収され、多くの修道院が閉鎖されました。この宗教改革により、ノルウェーの宗教的生活と社会構造が大きく変化したのです。
宗教改革と同時に、ノルウェーは政治的にもデンマークにさらに従属していきました。1536年、デンマークはノルウェーを正式に属国として位置付け、ノルウェーはデンマークの統治下に置かれることになりました。これにより、ノルウェーの独自の王権は消滅し、行政や司法もデンマークの影響下で進められるようになります。ノルウェーはデンマーク王国の一部としての性格を強め、独立性を失うこととなったのです。
16世紀のノルウェーは、宗教改革とデンマーク支配の強化によって、国内の宗教と政治が大きく変革した時代であり、ノルウェーの独自性が弱まる一方で、デンマークとの結びつきが一層強まった時期といえます。
1523年 デンマーク=ノルウェー連合王国の成立
「ストックホルムの血浴」を受け、スウェーデンがカルマル同盟から抜け独立したことで、デンマーク=ノルウェー連合王国が成立した。この連合王国は、デンマークとノルウェーが単一の君主の下で統治される形態であり、両国の政治的・経済的な統合が進められた。デンマーク=ノルウェー連合は、北欧における強力な政治勢力として影響力を持ち続け、地域の安定と繁栄に寄与した。
この連合王国は19世紀初頭まで続き、その間に多くの改革や発展が見られましたが、ナポレオン戦争後の条約により解体され、ノルウェーはスウェーデンとの同君連合に移行することになりました。
1537年 宗教改革/ノルウェー国教会の成立
16世紀になるとドイツで宗教改革が起こる。その影響でデンマークでは1537年に教会がルター派に再組織化され、その支配下にあるノルウェーもルター派の国家となった。同年ノルウェー国教会が成立した。
17世紀
17世紀のノルウェーは、デンマーク支配の強化と三十年戦争の影響を受けた時代であり、宗教的・政治的な変動が続きました。この時期、ノルウェーはデンマーク=ノルウェー連合王国の一部として統治され、独自の政治的・経済的な影響力は弱まりました。
17世紀を通じて、ノルウェーはデンマーク王国の支配下にあり、その影響力はますます強まりました。行政や司法のシステムはデンマークの法制度に基づいて運営され、ノルウェーの政治的な独立性はほとんど失われていきました。また、経済的にもデンマークに依存する状況が続き、ノルウェーは北海交易や漁業を中心とした経済活動を展開しましたが、収益の多くはデンマークへ流れ込むこととなりました。
17世紀前半に勃発した三十年戦争(1618年-1648年)は、デンマーク=ノルウェー連合王国にとっても大きな影響を及ぼしました。ノルウェーもデンマークと共にこの戦争に巻き込まれ、軍事的な負担を強いられました。戦争によって経済は疲弊し、国内の社会的・経済的状況は一層厳しいものとなります。また、戦争後のウィーン条約によってノルウェーの地位に大きな変化はなかったものの、デンマークの影響力がさらに強まったことは確かです。
17世紀の終盤には、ノルウェーの農民たちがデンマーク王国に対する不満を募らせ、いくつかの農民反乱が発生しました。特に、税の重圧や農地の管理に対する不満が原因となり、反乱が各地で勃発。これらの反乱は、ノルウェー社会の不安定さを象徴するものであり、デンマークとの関係にも緊張をもたらしましたが、最終的にはデンマーク側によって鎮圧されました。
17世紀のノルウェーは、デンマークの強力な支配と三十年戦争の影響下で政治的・経済的な困難を経験した時代であり、農民反乱や社会的不安定が表面化する中、ノルウェーの独立性がますます希薄になっていった時期といえます。
1660年 絶対王政の導入
デンマーク王フレデリク3世は様々な制度改革を行い、絶対王政を確立した。これにより、デンマーク=ノルウェー連合王国は、強力な中央集権的統治体制を持つようになり、貴族の特権が制限され、王権が大幅に強化された。この改革は、国家の安定と効率的な統治を目指したものであり、経済や行政の近代化も進められた。絶対王政の下で、デンマークとノルウェーはより緊密な統治関係を維持し、北欧における重要な政治勢力としての地位を確立。両国の社会や経済も発展し、国家の繁栄が続いた。
18世紀
18世紀のノルウェーは、デンマーク支配下での安定と経済発展が進んだ時代であり、啓蒙思想と近代化の兆しが見え始めました。この時期、ノルウェーは引き続きデンマーク=ノルウェー連合王国の一部として統治されていましたが、徐々に独自の文化と経済の発展が見られるようになったのです。
18世紀を通じて、ノルウェーはデンマーク王国の支配下で比較的安定した時代を迎えました。デンマークは中央集権化を進め、ノルウェーの行政や司法はデンマーク王室の管理下に置かれました。しかし、この時代には政治的な安定が保たれたため、国内で大規模な紛争や内戦は発生せず、社会は比較的平穏を保ちました。
18世紀は、ノルウェー経済が漸進的に発展した時期でもありました。特に、林業や漁業が主要産業として成長し、木材や魚の輸出が拡大。ノルウェーの港町は、これらの輸出産業を支える中心地となり、商業活動が活発化しました。また、鉱業も発展し、特に銀鉱山が経済に貢献しています。これにより、ノルウェーはヨーロッパの貿易ネットワークにおいて一定の役割を果たすようになったのです。
18世紀後半には、啓蒙思想がノルウェーにも広まり、教育や科学への関心が高まりました。多くの学校や教育機関が設立され、知識人たちが新しい思想や科学的発見に触れる機会が増加。これにより、ノルウェー社会は文化的にも発展し、次の世紀に向けた近代化の基礎が築かれていきました。
18世紀のノルウェーは、デンマーク支配下での政治的安定と経済発展が進んだ時代であり、啓蒙思想と文化の発展を通じて、次の近代化への基礎を築いた時期といえます。
1788年 土地緊縛制の廃止
農民が保有地から移転することを規制する土地緊縛制が廃止される。この改革により、農民はより自由に土地を移転し、農業経営の選択肢が広がった。土地緊縛制の廃止は、農民の生活条件の改善と農業生産性の向上に寄与し、農業改革の重要な一環として位置づけられた。
1800年 武装中立同盟の締結
デンマーク=ノルウェーは、スウェーデン、ロシア帝国と手を結び武装中立同盟を締結。この同盟は、ナポレオン戦争期における中立政策を維持し、戦争の影響を最小限に抑えることを目的としていた。武装中立同盟により、デンマーク=ノルウェーは自国の安全保障を強化し、戦時における貿易や経済活動を保護することを図った。この同盟は、北欧諸国間の協力と結束を象徴するものでもあった。
|
|
|
近代ノルウェー
19世紀になるとキール条約(ナポレオン戦争後結ばれた国際条約)によってデンマーク支配からは解放されたものの、今度はスウェーデンに領土を割譲されてしまいます。しかし20世紀になると独立運動が加熱し、国民投票によりスウェーデンとの関係解消を宣言します。これを承認しないスウェーデンと開戦一歩手前までいきましたが、ヨーロッパ列強からの支持も得たことでノルウェー王国」として正式に独立を達成することができたのです。
その後のノルウェーは、基本的にヨーロッパで起こる戦争に深入りせず、中立の立場をとるようになります。しかし第二次世界大戦では、中立の立場をとっていたにも関わらず、ドイツ軍に占領され、ドイツ降伏を迎えるまで抵抗運動が繰り広げられました。こういった経験を踏まえて、戦後は安全保障のための伝統的な中立政策を放棄し、北大西洋条約機構(NATO)の創立メンバーとして原加盟国になるなど立場を明確にしています。
19世紀
19世紀のノルウェーは、デンマーク支配からの解放と独立運動の高まりが進んだ時代であり、政治的・文化的な変革が急速に進行しました。この時期、ナポレオン戦争後にノルウェーはデンマークから解放され、スウェーデンとの同君連合下に置かれましたが、次第に独立に向けた動きが活発化していったのです。
1814年、ナポレオン戦争の結果として、ノルウェーはデンマークから解放され、スウェーデンとの同君連合が成立しました。この連合下でノルウェーは独自の憲法を制定し、国内自治を一定程度保ちながらスウェーデン王が国家元首となる体制が取られました。これにより、ノルウェーは長年のデンマーク支配から脱却し、新たな政治体制のもとで国の再建に着手したのです。
19世紀後半になると、ノルウェー国内で独立運動が活発化し、国民意識が高まります。特に文学や芸術の分野では、ノルウェーの自然や歴史を題材とした作品が数多く生まれ、これがナショナリズムの高揚に寄与しました。また、経済の発展と共に中産階級が台頭し、政治改革の要求が高まったことも重要です。これにより、ノルウェー社会は次第に民主主義的な基盤を固めていったのです。
19世紀のノルウェーは、デンマークからの解放とスウェーデンとの同君連合を経て独立運動が高まり、1905年の完全独立への基盤を築いた時期であり、政治的・文化的に重要な変革を遂げた時代といえます。
1814年 キール条約の締結/スウェーデン=ノルウェーの成立
ナポレオン戦争でデンマークが敗戦国となったことで、キール条約によりノルウェーはスウェーデンに割譲された。
20世紀前半
20世紀前半のノルウェーは、中立政策の維持とナチス・ドイツによる占領という激動の時代であり、国際的な緊張と戦争の影響を大きく受けました。この時期、ノルウェーは第一次世界大戦の後、中立を保ちながらも、第二次世界大戦でナチス・ドイツに占領されるという苦難に直面したのです。
第一次世界大戦(1914年-1918年)の間、ノルウェーは中立を維持しましたが、戦争による経済的影響は避けられませんでした。特に海運業が戦時中に活発化し、ノルウェーの経済に貢献する一方、戦後は貿易の縮小と経済的な困難が続いたのです。また、戦後の国際秩序の中で、ノルウェーは国際連盟に加盟し、平和維持と国際協力を推進する立場を取りました。
第二次世界大戦が勃発すると、ノルウェーは再び中立を宣言しましたが、1940年4月9日、ナチス・ドイツがノルウェーに侵攻し、ノルウェーは占領下に置かれることとなります。国王ホーコン7世と政府はロンドンに亡命し、そこで亡命政府を樹立。国内では、レジスタンス運動が活発化し、地下組織やゲリラ活動を通じてナチスに抵抗を続けました。占領下での厳しい統制と弾圧にもかかわらず、ノルウェー国民の抵抗意志は強く、最終的には連合軍の勝利とともに1945年に解放を迎えることになります。
第二次世界大戦後、ノルウェーは復興に向けた努力を開始しました。特に、戦争中に破壊されたインフラの再建と経済の復興が急務となりました。また、1945年に設立された国際連合(UN)の創設メンバーとして、ノルウェーは国際社会への復帰を果たし、積極的な外交政策を展開しました。
20世紀前半のノルウェーは、二度の世界大戦を経て、ナチス・ドイツの占領と抵抗運動を経験しながらも、戦後の復興と国際社会への復帰に向けた基盤を築いた時代であり、国家としての存続と再生を果たした時期といえます。
1905年 スウェーデンからの独立/ノルウェー王国の成立
スウェーデンとの同君連合の解消を宣言し、国民投票の結果とスウェーデンとの交渉の結果、無血の独立を果たす。現在に続く立憲君主制国家ノルウェー王国が成立した。
1913年 女性参政権の導入
女性に国政選挙権が与えられる。ニュージーランド、オーストラリア、フィンランドに次ぎ世界で四番目。現在ノルウェーは男女平等先進国の一つとされている。
1940年 ノルウェーの戦い
39年に第二次世界大戦が開始され、ノルウェーは中立を表明するもドイツ軍の侵攻を受ける。結果ナチス・ドイツに国土を占領されてしまい、ノルウェー政府と王家はイギリスに亡命した。
1945年 第二次世界大戦の終結
ナチス・ドイツの降伏に伴い、ノルウェーは解放。ノルウェー政府と王家は帰還を果たし、独立を回復した。
|
|
|
現代ノルウェー
現代ノルウェー史は、第二次世界大戦後から始まります。ノルウェーは1940年にナチス・ドイツに占領されましたが、1945年の解放後、迅速に復興を遂げました。1949年には北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、冷戦期には西側諸国の一員として安全保障体制を強化しました。
1950年代以降、北海での石油と天然ガスの発見と開発がノルウェー経済を大きく変えました。これにより、ノルウェーは一躍世界有数のエネルギー輸出国となり、高い生活水準と充実した福祉制度を支える財源を得ました。
1994年には欧州経済地域(EEA)に加盟し、EUとの経済的な結びつきを強化しましたが、EU加盟には慎重な姿勢を保ち続けています。近年、ノルウェーは環境保護や持続可能なエネルギー政策にも積極的に取り組んでおり、再生可能エネルギーの利用拡大を進めています。
ノルウェーは国際的な平和維持活動や人道支援にも積極的に参加しており、グローバルな問題解決に貢献しています。このように、豊かな資源と強力な福祉制度を基盤に、国際社会で重要な役割を果たし続けています。
20世紀後半
20世紀後半のノルウェーは、戦後復興と国際的な地位の確立が進んだ時代であり、福祉国家の発展と北大西洋条約機構(NATO)への加盟が重要な特徴です。この時期、ノルウェーは経済的繁栄を遂げ、国際社会での影響力を強めながらも、国内外のさまざまな課題に直面しました。
第二次世界大戦後、ノルウェーはインフラの復興と経済成長を目指し、福祉国家の構築に力を注ぎました。1950年代から1960年代にかけて、政府は医療、教育、住宅などの分野で充実した社会福祉制度を整備しました。この福祉国家モデルは、ノルウェー社会の安定と高い生活水準の基盤となり、ノルウェーは「福祉国家」の代表例とされるようになりました。
1949年、ノルウェーは北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、西側陣営の一員としての立場を確立しました。冷戦期には、ノルウェーはNATOの一員として軍事的防衛力を強化しつつ、平和主義的な外交政策も展開。特に、ノーベル平和賞の授与国としての役割を通じて、国際平和に貢献する姿勢を強調しました。
1960年代後半には、北海で石油と天然ガスが発見され、ノルウェー経済は急成長を遂げました。1970年代には石油産業が本格化し、その収益は国の財政を豊かにし、社会福祉のさらなる充実や教育、技術開発に資金を投じる原動力となりました。また、石油収益を慎重に管理するための「ノルウェー政府年金基金(オイルファンド)」が設立され、経済の安定を図るための重要な役割を果たすこととなりました。
20世紀後半のノルウェーは、戦後復興と福祉国家の確立を基盤に、NATO加盟や石油産業の発展を通じて経済的繁栄と国際的な地位の確立を実現した時代であり、現代の豊かなノルウェー社会の基礎を築いた時期といえます。
1959年 EFTAに加盟
ヨーロッパ共同体(EEC)に加盟を拒否されたイギリスを中心に結成された欧州自由貿易連合(EFTA)に加盟。加盟国間の自由貿易と経済統合の促進を目的とする。発足は60年。
1969年 北海油田の発見
ノルウェー領北海で大規模な油田が発見され、これによりノルウェーは主要な石油生産国となる。石油産業の発展はノルウェー経済に大きな影響を与え、国の繁栄を支える基盤となった。
1972年 EEC加盟に関する国民投票
ノルウェー政府はヨーロッパ共同体(EEC)への加盟を目指すが、国民投票の結果、加盟は否決される。ノルウェーはEFTA加盟国としての立場を維持することとなる。
1994年 欧州経済領域(EEA)に加盟
ノルウェーは欧州経済領域(EEA)に加盟し、EUの単一市場に参加することで経済的な結びつきを強化。これにより、ノルウェーはEU加盟国と同等の経済的利益を享受しつつ、独立を維持することが可能となった。
2011年 オスロでの連続テロ事件
オスロ市内とユトヤ島で連続テロ事件が発生し、多くの犠牲者が出る。この事件はノルウェー国内外に大きな衝撃を与え、国内の安全保障政策の見直しや、社会の団結を強化する契機となった。
2015年 パリ協定の採択
ノルウェーは国際的な気候変動対策の一環として、パリ協定に署名し、温室効果ガスの削減目標を設定。再生可能エネルギーの推進や環境保護に力を入れることで、持続可能な社会の実現を目指す。
2020年 COVID-19パンデミックへの対応
ノルウェーも世界的なCOVID-19パンデミックの影響を受けるが、迅速な対応と国民の協力により感染拡大を抑えることに成功。経済的支援策やワクチン接種の推進により、社会の回復を図る。
|
|
|