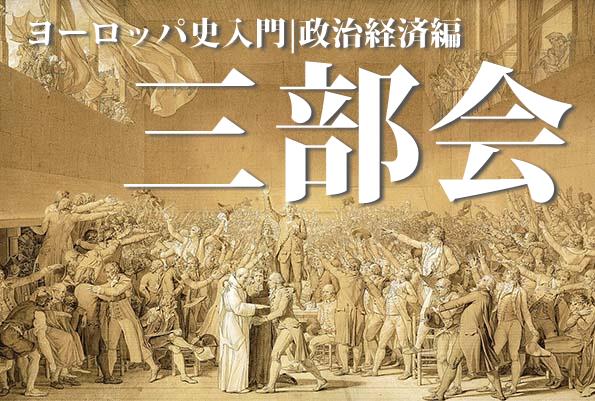
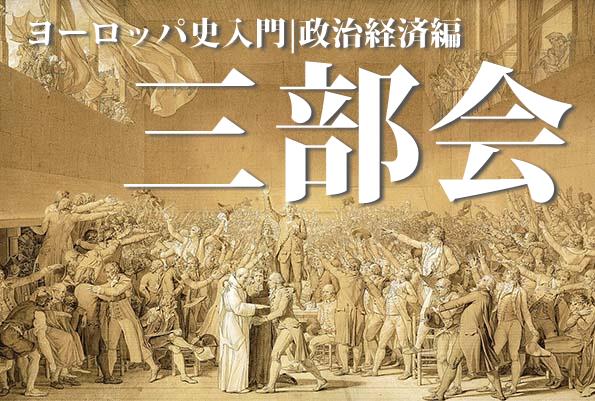
三部会とは
第三身分とは何か。すべてである。
これまで政治的には何であったか。無である。
今や何を求めるのか。何かたらんことを。
─ アベ・シェイエス『第三身分とは何か』(1789)
三部会とは、14世紀初頭から始まったフランスにおける身分制議会のことです。聖職者・貴族・平民(有力都市の商人や農民)という三つの身分の代表者から構成され、課税を始めとして、王国の様々な問題について議論を行うために創設されました。全国三部会(エタ・ジェネロ)と地方三部会(エタ・プロバンシォ)に分けられますが、たんに「三部会」といった場合、通常は全国三部会のことを指します。
|
|
|
|
|
|
三部会の歴史
1302年、教皇と対立するフィリップ4世(在位:1285年−1314年)が、聖職者への課税強化をめぐり国民の支持を得るためパリのノートルダム大聖堂に招集したのが三部会の始まりとされています。その後百年戦争(1337年〜1453年)が始まると、戦費をかき集めるために、頻繁に開催されるようになり、意思決定機関としての重要度が高まっていきました。ルイ13世による絶対王政確立後はしばらく招集されていませんでしたが、1789年5月、課税に反発する貴族からの求めで170年ぶりに開催。しかし議決方法をめぐり紛糾したため、第三身分が国民議会として分離し、フランス革命(1789〜95年)の勃発を準備することになるのです。

1789年に175年ぶりに開かれた三部会の様子
起源と中世の展開
1302年:フィリップ4世(端麗王)が初めて三部会を招集
教皇と対立する中、国王の政策に国内の正統性を与えるために開かれたのが最初。以降、必要に応じて不定期に開催される。
14〜15世紀:戦費や税の承認、国内の危機対応などで断続的に招集
ただし、実質的な発言力は限定的で、王権が強まるにつれ形式化していく。
ルネサンス以降の衰退
16世紀以降:絶対王政の台頭により、三部会の重要性は低下
ルイ13世、ルイ14世の時代には三部会がほぼ招集されなくなる(国王が絶対的な立法・課税権を握るようになったため)。
1614年:ブルボン朝最後の三部会が開かれる
これ以降、三部会は約175年間も招集されなかった。
革命の引き金
1789年5月:ルイ16世が財政危機の打開策として三部会を召集
しかし、身分ごとの一票制(第一身分1票、第二身分1票、第三身分1票)のままでは第三身分が不利だと反発。
1789年6月:第三身分が「国民議会」の結成を宣言
これがフランス革命の発端となる。三部会はもはや旧制度の象徴とされ、革命によって廃される。
三部会の議決方法
三部会は身分制議会です。第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、第三身分(平民)が、身分ごとに1票の議決権を持っており、ある議題に対して、2票の賛成(反対)を得た決定が通るというもの。しかしこの「身分別議決法」にはある致命的な欠点があります。それは上流階級の利権を揺るがすような議題では、第三身分の意見は絶対に通らないということです。第一身分、第二身分は高確率で反対票に入れるので、第三身分の議員がどれだけいたところで、1身分1票しか入れられないので、2対1で絶対に負けるからです。
なので、1789年に170年間ぶりに三部会が開催された際、この時代錯誤の議決方法が問題視されました。第三身分は一人一票による多数決を主張しましたが、利権を守りたい第一身分、第二身分は当然反対します。議論の折り合いはつかず、第三身分は三部会から離れ、のちにフランス革命の導火線となる、独自の議会「国民議会」を発足させることとなったのです。
三部会の人数
三部会に招集される代表者の人数は、誰の治世かで異なりました。
| 開催年 | 代表人数 | |
|---|---|---|
| シャルル5世 | 1356年 | 800人(内第三身分が400人) |
| シャルル8世 | 1484年 | 285人 |
| アンリ4世 | 1593年 | 120人 |
| ルイ13世 | 1614~15年 |
聖職者:150人 貴族:132人 第三身分:182人 |
| ルイ16世 | 1789年 |
聖職者:291人 貴族:270人 第三身分:578人 |
三部会の意義
「三部会」が果たした意義は以下のようにまとめられます。
国王と身分階級との交渉の場
三部会は、封建的な身分制社会において、国王が各身分の代表と協議し、税制や法令などに正当性を持たせる手段でした。特に新税の賦課など、王権の拡大と国政運営に民意の同意を得る目的がありました。
絶対王政と国民主権の転換点
1789年、ルイ16世が財政難から約175年ぶりに招集した三部会は、第三身分代表が「国民議会」の結成を宣言し、旧制度(アンシャン=レジーム)を否定する革命的な転機となりました。これがフランス革命の発火点となったのです。
社会の不平等構造を象徴
三部会では各身分が1票ずつ持ち、人口の大多数を占める第三身分の意見が過小評価されていたことが、不平等への不満を噴出させる要因にもなりました。この構造が第三身分の「政治的覚醒」を促したとされます。
つまり、三部会は旧制度の象徴であると同時に、そこから革命へと至る歴史的な転換点として大きな意義を持つ制度でした。
|
|
|
|
|
|



