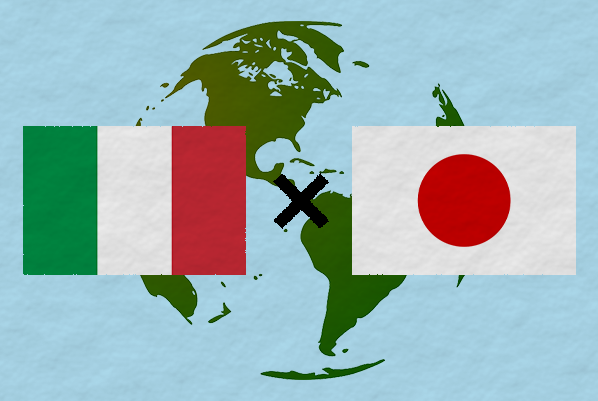![]()
音楽の世界で使われる音階の名前、「ドレミファソラシ」は私たちにとって非常に馴染み深いものですが、実はこれらはイタリア語に由来しています。では、なぜ音階の名前がイタリア語になったのでしょうか。その歴史的な背景を探っていきましょう。
中世イタリアのラテン語賛美歌
"ドレミファソラシ"という音階の起源は、中世イタリアのラテン語賛美歌「Ut queant laxis」に遡ります。この賛美歌の各節(節頭)の音が、後の西洋音楽の音階に対応しており、「Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La」は賛美歌の各行の冒頭の音節をとったものなのです。なお「Si」は後に追加され、最初の二行の頭文字をとって作られました。
イタリアの音楽理論家グイド・ダレッツォ
この音階名を最初に提唱したのは、11世紀のイタリアの音楽理論家、グイード・ダレッツォ(992年 - 1050年)です。ダレッツォは音楽の教育を簡素化するためにこのシステムを導入し、やがてヨーロッパで広く受け入れられ、音楽理論の基礎となったのです。
「Ut」から「Do」へ
元々、"ド"の部分は「Ut」と呼ばれていましたが、16世紀のイタリアの音楽研究家が「Ut」を「Do」に変更しました。これは「Do」の方が発音しやすく、歌いやすいというシンプルな理由からです。
"ドレミファソラシ"という音階は、中世イタリアの賛美歌と、その後の音楽研究家たちの働きかけによって生まれました。これらの音階の名前は、世界中の音楽教育や表現に使われ、グローバルな音楽コミュニケーションの一部となっているのです。