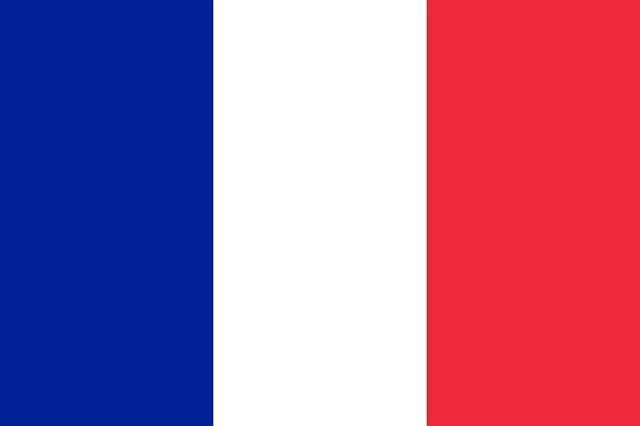第二次世界大戦イタリアが参戦した理由は?

イタリア参戦を主導したムッソリーニ
第二次世界大戦とは、1939年9月から1945年8月にかけて、文字どおり世界中を巻き込んで行われた、史上最大規模の戦争です。枢軸国(イタリア・ドイツ・日本など)と、連合国(アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国など)が、地球規模で激突しました。きっかけは、ナチスドイツによるポーランド侵攻(1939年9月)。これにイギリスとフランスが対独宣戦を行い、戦争は一気に現実のものとなります。その後は独ソ戦、そして太平洋戦争へと広がり、戦線は雪だるま式に拡大。反ファシズム、帝国主義、民族自決といった要素が複雑に絡み合う、非常に多面的な戦争でした。
そんな大きな流れの中で、イタリアはムッソリーニ率いるファシスト政権のもと、枢軸国の一員として参戦します。ただし、ここからがイタリアらしいというか、一筋縄ではいきません。戦況が悪化するにつれて国内の不満はどんどん膨らみ、1943年にはついにムッソリーニが失脚。イタリアは連合国と休戦協定を結び、戦争の後半では立場を変え、連合国側として再び戦場に立つことになります。まさに大転換。国の進む向きが、途中でガラッと変わった瞬間でした。
さらに北部イタリアでは、ドイツ軍に対抗するパルチザン(抵抗運動)が活発化します。一般市民も巻き込みながら続いたこの戦いは、連合国軍の進撃と歩調を合わせるかたちで展開され、最終的にはイタリア全土の解放へとつながっていきました。イタリアは第二次世界大戦の中で、立場を変えながらも自らの行く末を模索し続けた国だった、と言えるでしょう。
ここから先では、イタリアがどのように参戦し、なぜ転じ、そしてどのように終戦を迎えたのか。その流れを、もう少し丁寧に追っていきます。
|
|
|
イタリアの戦い前半戦
戦争が始まった当初、イタリアは「勝てそうな側につく」という判断のもと、比較的遅れて参戦しました。
ですが、その選択は決して盤石な準備に裏打ちされたものではなく、むしろ楽観的な見通しに支えられた賭けに近いものでした。
ここでは、イタリアが枢軸国として戦った前半戦に焦点を当て、参戦の背景と、早い段階で露呈していく誤算の数々を追っていきます。
参戦|勝ち馬に乗れるという甘い読み

アンシュルス後、ヒトラーとムッソリーニにより行われたウィーン市内のパレード
第二次世界大戦が始まった1939年9月の時点で、イタリアは形式上、枢軸国の一員としてドイツ側に立つ立場にありました。ただし「じゃあ、すぐ戦おう!」という空気だったかというと、実はそうでもありません。当時のイタリア指導層は、この戦争への本格参戦にかなり慎重でした。というのも、第一次大戦後の不況の影響はまだ色濃く残っており、軍備も経済力も正直いって心もとない状態。おまけに、重要な貿易相手である米英と敵対するリスクは、どう考えても割に合わなかったのです。
ところが状況は、ドイツ軍の電撃的な快進撃によって一変します。とくにフランスがあっという間に追い詰められていく様子を目の当たりにすると、「今なら勝ち組に乗れるのでは?」という空気が軍部や王党派の間に広がっていきました。参戦に消極的だった人々が、次々と態度を変えていく──そんな、風向きが変わる音が聞こえてくるような局面です。
短期決戦想定で宣戦布告
そしてフランスの敗北がほぼ確実となり、さらにアメリカとソ連が中立を保っているのを確認すると、イタリアは「これは短期決戦で終わる」と判断します。想定されたのは、イギリスもいずれ降伏し、戦争は早々に終結するというシナリオ。その読みのもと、イタリアは1940年6月10日、イギリスとフランスに宣戦布告しました。
イタリアの参戦は、周到な準備の結果というより、「今なら間に合う」という楽観的な判断に強く支えられていた、と言えるでしょう。ここから先、その判断がどれほど重たい意味を持つことになるのか──前半戦は、まだ誰も深く実感していなかったのです。
苦戦|見通しの甘さが一気に表面化

アフリカ戦線/エル・アラメインの戦いで、イギリス軍に連行されるイタリア軍捕虜
ところが、開戦前に描いていたシナリオは、あっさりと崩れていきます。短期決戦どころか、戦えば戦うほど不利になる展開。イタリア軍の近代化の遅れは想像以上に深刻で、装備も指揮体制も、現代戦に対応しきれていませんでした。理屈では数で押せるはずの場面でも、現実はそう簡単にはいかなかったのです。
戦場で露呈した現実
とくに顕著だったのがアフリカ戦線です。兵力の数では有利に立ちながらも、機動力と統率に勝るイギリス軍に押し返され、主導権を完全に失っていきました。さらにバルカン半島では、当初「格下」と見ていたギリシャ相手にまさかの大苦戦。想定外の消耗戦となり、イタリア軍の限界が次々と露わになります。作戦の甘さ、準備不足、そのツケが一気に回ってきた形でした。
追い打ちをかけたのが、アメリカの参戦です。これにより戦争は長期戦が避けられない状況となり、資源に乏しいイタリアは急速に追い込まれていきます。燃料も物資も足りず、次第にドイツへの依存度が高まり、国家としての自由度は目に見えて低下していきました。実態は、対等な同盟国というより、ドイツの影響下に置かれた存在へと変わっていったのです。
その影響は国内にも直撃します。戦局の悪化とともに経済は疲弊し、国民生活はじわじわと苦しくなっていきました。やがて人々の間には、ムッソリーニ政権への不満と、戦争そのものに対する厭戦ムードが広がっていきます。前線での敗北と国内の疲弊が同時進行で進んだことが、イタリアを決定的に追い詰めていった──そんな空気が、この時期のイタリア全体を覆っていたのです。
休戦|踏みとどまれなくなった分岐点

ハスキー作戦でドイツ軍の抵抗を受け炎上する連合軍の輸送船
1943年に入る頃には、戦争全体の流れは明らかに連合国側へと傾いていました。前線の敗北が積み重なり、国内経済も限界に近づく中、これまで強硬姿勢だったファシスト党や王党派の内部からも、「もう続けられないのでは」という声が少しずつ上がり始めます。空気の変化。勝ちを信じていた人々の中にも、迷いが生まれていたのです。
決断を迫られる政権中枢
それでもムッソリーニは、なおドイツと運命を共にする道を選び、戦争継続を主張し続けました。しかし、国内で方針がまとまりきらないその隙を、連合国は見逃しません。対ドイツ戦略における要衝として、イタリアは極めて重要な位置にあり、ウィンストン・チャーチルが「ヨーロッパの下腹部」と表現したのも、その脆さを見抜いてのことでした。
こうして連合軍は、シチリア上陸作戦(ハスキー作戦)を敢行します。疲弊しきったイタリア軍には、これを食い止める力はほとんど残っておらず、上陸はあっさりと許されてしまいました。この時点で、多くの人が悟ったのです。これ以上の継続は、国そのものを危うくする──と。
その結果、水面下では休戦派を中心に、連合国との秘密裏の休戦交渉が始まりました。表向きはまだ戦争を続けながら、裏では出口を探る。戦場の敗北と政治の迷走が重なり、イタリアはもはや引き返せない局面に立たされていた、そんな瞬間だったと言えるでしょう。
降伏|体制そのものが崩れた瞬間

ムッソリーニ解任後、首相後任となったピエトロ・バドリオ
戦況の悪化がもはや隠しようのない段階に入ると、ついに政権の中枢でも「このままでは国がもたない」という認識が共有され始めます。イタリアを破滅の瀬戸際に追い込んだとして、ファシズム大評議会はムッソリーニに対し、首相退任を求める決議を突きつけました。これが、いわゆるグランディ決議です。長く続いた独裁体制に、初めて明確な「ノー」が突きつけられた瞬間でした。
王の判断と政権交代
この決議を支持したのが、当時の国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世です。王国の存続そのものを危惧した国王は、もはやムッソリーニを守りきれないと判断しました。その結果、評議会では賛成多数となり、ムッソリーニは首相の座を追われ、さらに逮捕という形で表舞台から姿を消します。かつて絶大な権力を握っていた指導者が、あまりにもあっけなく失脚した瞬間でした。
こうして新たに首相に就任したのが、ピエトロ・バドリオです。表向きは「戦争継続」を掲げながらも、実際には戦争からの離脱を模索する立場にありました。体制は維持されているように見えて、その内側では大きな転換が進んでいたのです。
ムッソリーニの失脚は、単なる指導者交代ではなく、ファシスト体制そのものが限界を迎えたことを意味していました。この出来事を境に、イタリアは「敗戦国としてどう終わるのか」という、まったく別の段階へと足を踏み入れていくことになります。
イタリアの戦い後半戦
ムッソリーニの失脚と休戦によって、イタリアは一見すると戦争から離脱したかのように見えました。
しかし現実には、そこから先のほうが、状況はさらに複雑で過酷なものへと変わっていきます。
ここからは、同盟崩壊、ドイツ軍の進駐、そして内戦へと突き進んでいく後半戦のイタリアを見ていきましょう。
「裏切り」|同盟が崩れたその瞬間

ヒトラーはイタリアの「裏切り」に怒り、すぐさまイタリアへ進軍を命じた
ムッソリーニの失脚は、戦争の流れを一気に動かしました。これを受けた連合国は、「イタリア政府が休戦し、無条件降伏した」とする内容を先回りする形で公表し、シチリア島からイタリア半島南部へと侵攻を開始します。バドリオ政権にとっては、まさに寝耳に水。準備も覚悟も整わないまま、事態は一気に表へと引きずり出されました。
降伏と宣戦、急転直下の選択
とはいえ、現実はあまりにも厳しいものでした。軍事的にも政治的にも、これ以上まともな抵抗ができる状況ではなく、バドリオ政権は1943年9月、連合国の要求を受け入れ、無条件降伏を受諾する声明を発表します。こうしてイタリアは正式に枢軸国を離脱し、翌10月には、かつての同盟国であったドイツに対して宣戦布告するという、劇的な立場の転換を行いました。
しかし、この決断は当然ながらドイツ側に衝撃を与えます。ヒトラーはこれを明確な「裏切り」と受け取り、即座に対応を決断。ドイツ軍は命令一下、北イタリアへと進軍を開始しました。かつて肩を並べていた同盟国が、今度は銃を向け合う存在へと変わったのです。
イタリアの降伏は戦争からの離脱ではなく、新たな戦争の始まりを意味していました。この瞬間から、イタリアは「解放」と「占領」が同時に進む、さらに複雑で過酷な局面へと突入していくことになります。
内戦|国が真っ二つに裂けた戦い

グラン・サッソ襲撃でドイツ軍によって解放されるムッソリーニ
1943年9月13日、失脚して拘束されていたムッソリーニは、ドイツ軍の特殊部隊による大胆な作戦によって解放されます。まさかの復活。ですが、かつてのようにローマで権力を振るう状況ではありませんでした。彼が向かったのは、北イタリアの町サロ。そこでドイツの後ろ盾を受け、イタリア社会共和国の建国を宣言します。
四つ巴の戦場
この動きによって、イタリアの状況は一気に複雑化します。南から進撃する連合国、北を掌握するドイツ軍、その傀儡国家としてのイタリア社会共和国、そして各地で活動を強めるパルチザン。複数の勢力が同時に存在し、それぞれが異なる目的で戦うという、極めて混沌とした内戦状態へと突入しました。もはや「どこが前線か」すら分かりにくい、国土全体が戦場のような状況です。
やがて北部防衛線は、連合国の想定以上の速さで突破されていきます。戦況は日に日に不利となり、1945年4月にはイタリア社会共和国の崩壊が決定的となりました。追い詰められたムッソリーニは、スイスへの亡命を図りますが、その試みは成功しません。国境にたどり着く前にパルチザンに捕えられ、裁判を待つこともなく処刑されました。
同じイタリア人同士が敵味方に分かれて戦ったこの内戦こそが、戦後まで重く影を落とす最大の傷跡となりました。第二次世界大戦の終盤、イタリアは外敵との戦い以上に、国内での分断という苦しい現実と向き合うことになったのです。
終戦|王国に幕が下りた日

王政廃止により国外追放となったウンベルト2世
1945年5月にドイツが、続いて8月には日本が降伏し、長く続いた第二次世界大戦はようやく終結を迎えました。戦火は止みましたが、イタリアにとって本当の意味での「戦後」は、ここからが始まりです。国は疲弊し、社会は分断され、そして統治のあり方そのものが問われる段階に入っていきました。
王制か、共和制か
戦後、サヴォイア王家は、ファシズム独裁体制に協力してきた責任を厳しく追及されます。「この王制を、このまま続けるべきなのか」。その問いに答えるため、国の進路は国民投票に委ねられました。結果は、わずかな差ながら王制廃止派が多数。この決定により、ウンベルト2世を含む王家は国外追放となり、長い歴史を持つ王国は静かに幕を下ろします。
こうしてイタリアは、共和制国家として新たな一歩を踏み出しました。独裁と戦争、内戦という重たい経験を背負いながらも、政治体制を根本から組み替え、再出発を選んだのです。第二次世界大戦の終結は、イタリアにとって「敗戦」ではなく、国家のかたちを作り直す出発点でもありました。現在のイタリア共和国は、この選択の延長線上に存在しているのです。
以上、イタリアの視点から第二次世界大戦の流れを見てきました。いかがでしたでしょうか。第二次世界大戦は、イタリアにとって国家の進路そのものを揺さぶる大きな転換点でした。枢軸国として戦争に踏み出し、途中で立場を変え、最終的には国内で内戦まで経験する──そんな激動の数年間は、決して一直線ではありませんでした。
ムッソリーニ政権の崩壊、ファシズム体制の終焉、そして王制から共和制への移行。これらはすべて、戦争の只中で起きた出来事であり、偶然ではありません。戦争という極限状況が、政治や社会の矛盾を一気に表面化させた結果だったと言えるでしょう。
もちろん、その代償はあまりにも大きなものでした。多くの犠牲、国土の破壊、そして人々の間に残った分断。しかしその一方で、戦後のイタリアは「同じ過ちを繰り返さないために、国のかたちを作り直す」という選択をします。民主的な制度を整え、平和を重視する国家へと舵を切ったのです。
第二次世界大戦は、イタリアにとって破壊の歴史であると同時に、新しい国家へ生まれ変わるための通過点でもありました。混乱と困難を乗り越えながら、一歩ずつ前に進んでいく。その姿勢こそが、戦後イタリアの歩みを形作っていったのです。
|
|
|