ハンガリー料理の歴史は遊牧民文化と農耕文化の融合に始まる。オスマン帝国やオーストリア帝国の影響を受けながら独自の食文化を築いた。 本ページでは、ハンガリーの歴史や文化、社会を理解する上で重要なこのテーマについて、より詳しく探っていこうと思う。
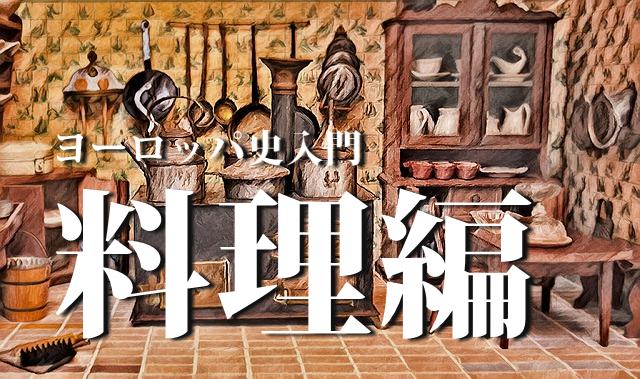
ハンガリー料理とパプリカ
ハンガリー料理においてパプリカは欠かせない存在だ。独自の風味と鮮やかな色合いが料理全体を特徴づけている。 本ページでは、ハンガリーの食文化や歴史、社会を理解する上で重要なこのテーマについて、より詳しく探っていこうと思う。

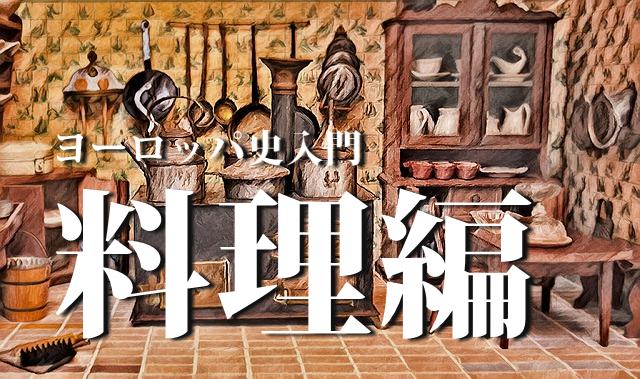

ハンガリー料理には、必ずと言っていいほどパプリカが使われています。パプリカは日本人にとっても、馴染みある食材ですが、この野菜はハンガリー発祥であり、故に「パプリカ」という呼称も実はハンガリー語なのです。
|
|
|
ハンガリーの人々は、オスマン帝国時代に流入した唐辛子を、長い歳月をかけて改良し、辛味の全くない唐辛子、パプリカを生み出しました。今現在はなんと150種以上のパプリカがあり、ハンガリーの人々にとっては、文字通り国民的な食料となっています。
|
|
|
ハンガリー人がパプリカを多用するのは、歴史的背景もありますが、その栄養価の高さも一因として挙げられます。パプリカには、ピーマンの約2倍のビタミンC、約3倍のカロテンが含まれており、肉食中心のハンガリー人の栄養バランスをとるのに、一役買っているのです。
聞きなれた栄養素「ビタミンC」は、アルベルト・セント=ジェルジというハンガリー出身の生理学者が、パプリカの果肉の中から初めて発見、抽出することに成功し、その功績により1937年にノーベル賞も受賞しています。
|
|
|