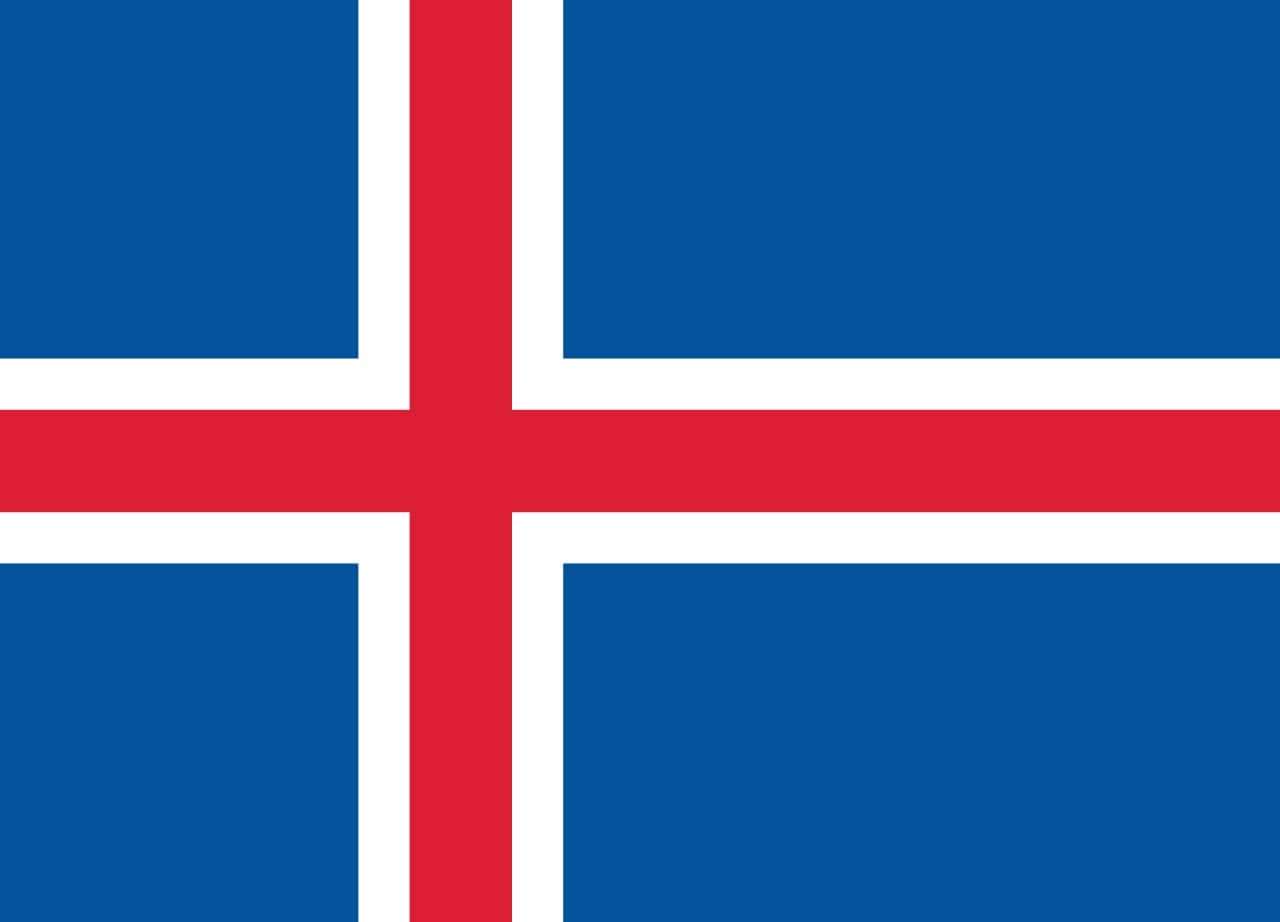フランスの憲法の特徴

フランスの国旗

フランスの国土
現在のフランスの憲法の正式名称は「フランス共和国憲法」といい、1958年10月4日に制定されたものですが、その起源はフランス革命と人権宣言の可決を経て、フランス最初の成文憲法として成立した1791年9月3日憲法にあります。ドゴール就任から始まった第五共和制の支柱となっている為、第五共和国憲法とも呼ばれており、前文+第1章~第16章で構成されています。
現フランスの、国会の権限よりも大統領(国民選出)の権限が強い「執行府優位型」の体制は、この第五共和国憲法制定にともない確定しました。前の第四共和国憲法において、国会の権限が強すぎて、政策がいっこうに決まらず、政治的停滞を招いたことの反省から草案された憲法です。
|
|
|
フランス憲法の前文
フランス第五共和制憲法の前文では、主に1789年のフランス人権宣言の尊重が謳われています。つまり前文は「人は、自由かつ権利において平等なものとして生まれ、かつ生存する」(人権宣言第1条)などの理念を継承し、フランスを自由で平等な民主的な国家と位置づける機能を有しています。また侵略戦争を目的とした武力行使の禁止を定めているのも前文の特徴です。
フランス憲法の歴史
|
|
|
1789年 人権宣言可決
フランス革命勃発後、国民議会により自由と平等を謳った人権宣言が可決された。フランス最初の成文憲法となった。
|
|
|
1791年 1791年9月3日憲法の制定
国民主権を基礎原理とした1791年9月3日憲法が制定された。この憲法により、立法権は国民議会が行使することが定められた。
|
|
|
1795年 共和国憲法制定
ロベスピエールによる恐怖政治が終息した後、両院制を定めた憲法が制定された。
|
|
|
1814年 1814年憲章の制定
ナポレオンの失脚後、復権を果たしたルイ18世が、欽定憲法として1814年憲章を公布。フランス革命前の絶対王政秩序に戻すことを目的としており、国王が国政上中心的役割を担うことが定められた。
|
|
|
1830年 1830年憲章の制定
七月革命により復古王政が打倒された後、1814年憲章の改正により1830年憲章が定められた。この憲章により、国王の独立命令権の廃止、検閲の廃止、三色旗の復活などが実現した。
|
|
|
1848年 1848年憲法の制定
二月革命により七月王政が打倒された後、1848年憲法が定められた。大統領制の採用と男子普通選挙による大統領の選出を定めたもの。
|
|
|
1852年 1852年憲法の制定
ルイ・ナポレオンによるクーデターで第二共和政が崩壊した後、1852年憲法が制定された。ナポレオン1世以来の帝政の復活を定めたもので、フランス第二帝政が創始した。(同時にほぼ同じ内容の帝国憲法を公布)
|
|
|
1875年 第三共和政憲法の制定
ナポレオンの失脚後、パリで成立した臨時政府により、1875年憲法(第三共和政憲法)が制定された。三権分立をとった上で、議会選出の大統領に「両院の解散権」など強い権限が与えられた。
|
|
|
1946年 第四共和政憲法の制定
第二次世界大戦終結後、第四共和政憲法が制定された。この憲法により大統領は権限を著しく弱めたのに対し、国民議会の権限は大きく拡大された。
|
|
|
1958年 第五共和政憲法の制定
クーデターでドゴールが政界に復帰した後、国民議会の権限が強すぎる為、政局不安定の原因になっていた第四共和国憲法を改正し、第五共和国憲法が制定された。国会の権限よりも大統領(国民選出)の権限が強い「執行府優位型」の体制が確立した。
|
|
|