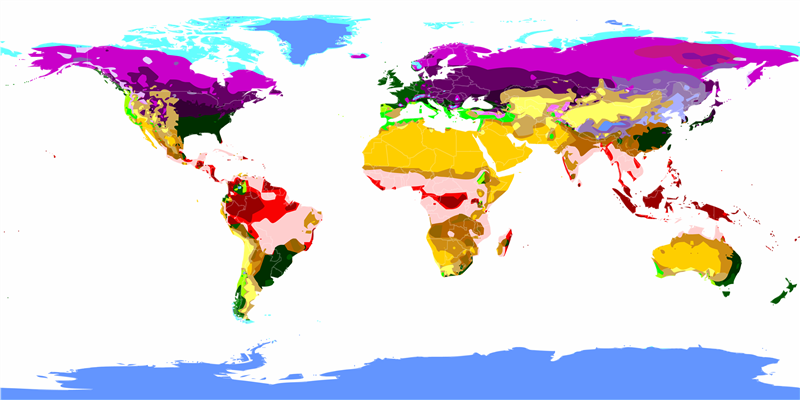亜寒帯気候の農業の特徴|栽培される主な農作物とは?

ライ麦
寒冷や貧弱な土壌でも育つ強靭な作物で、北欧などの亜寒帯気候でも栽培されている
出典:Photo by LSDSL / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Ear_of_rye』より
亜寒帯気候──つまり、夏が短くて冬が長く寒い地域では、「農業は難しいのでは?」というイメージを持たれがち。でも実際には、この厳しい環境に合わせたたくましい農作物たちが、ヨーロッパの北部や東部でしっかりと根を張ってきたんです。今回は、亜寒帯気候で育てられる代表的な農作物と、その背景にある農業の工夫について紹介します。
|
|
|
|
|
|
寒さに強い「穀物」
亜寒帯気候の農業といえば、まずは穀物。寒さに強く、短期間で育つ種類が選ばれています。
ライ麦
ライ麦は、寒冷地のエース的存在。成長期間が短く、痩せた土壌でも育つので、フィンランドやロシア西部、バルト三国などで広く栽培されています。ライ麦パンやクラッカーは、こうした地域の主食として定着しています。
オート麦(えん麦)
オート麦も、冷涼な気候に向いている穀物。特にスコットランドやバルト地域で重要視されており、ミューズリーやオートミールなど、加工して食べる文化が根づいています。
|
|
|
保存性に優れる「根菜類」
地中で育つ根菜類は、霜に強く保存性にも優れているため、亜寒帯地域では非常に重宝されています。
ジャガイモ
ジャガイモは、19世紀以降ヨーロッパ全域に広がった作物ですが、とくに亜寒帯地域では主食に近い存在。フィンランドやベラルーシ、ポーランドでは、「おかずよりまず芋!」という家庭も多いとか。
テンサイ(ビート)
テンサイ(甜菜)は、砂糖を採るために育てられる根菜で、比較的冷涼な気候に適しています。バルト三国やドイツ東部、ロシア西部などで栽培され、砂糖大根とも呼ばれるこの作物が、現地の糖分供給を支えてきました。
|
|
|
短い夏を活かした「野菜類」
夏の気温はさほど高くないものの、日照時間が長いのが亜寒帯の特徴。それを活かして野菜も栽培されています。
キャベツやニンジン
キャベツやニンジンは、冷涼な気候を好む代表的な野菜。しかも保存性が高いため、冬の食料確保にも役立ちます。ロシアの「シチー」やドイツの「ザワークラウト」など、漬物・煮込み文化との相性も抜群。
カブやビーツ
ビーツは、特に東ヨーロッパで人気の野菜。ウクライナのボルシチに欠かせない真っ赤な野菜ですね。カブも同様に、寒さに強く、浅根性で育てやすい作物として利用されています。
|
|
|
畜産のための「牧草・飼料作物」
寒冷地では、畜産のための牧草栽培や飼料作物もまた、重要な農業要素となっています。
クローバー・ティモシーなどの牧草
夏にしっかり育つクローバーやティモシーといった牧草が、牛や羊の餌として欠かせません。これらは乾燥させて冬の飼料とするため、夏の短期間でどれだけ収穫できるかが勝負になります。
サイレージ用トウモロコシ
一部地域では、気候が許す範囲でトウモロコシも育てられ、サイレージ(発酵飼料)として牛の餌に使われます。ただし、穀物用としてではなく、早刈りしての利用が一般的です。
亜寒帯気候でも、工夫次第でしっかりと農業は成立するんです。寒さに負けない作物たちが、この地域の食文化や暮らしを支えてきました。厳しい自然のなかで選び抜かれたラインナップだからこそ、その価値はどれも実用的で、たくましいんですね。
|
|
|