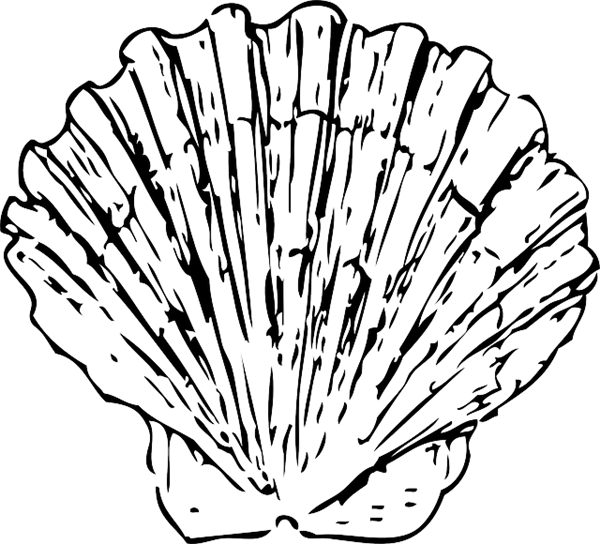陶片追放
陶片追放は自由の名のもとに行われた恐怖政治であった。
だがそれは、権力者ではなく、市民が主導する恐怖であった。
─ 古代史家・モーゼス・フィンリー『古代ギリシアの民主主義と政治的思想』(1973)
陶片追放は、古代ギリシア(主にアテナイ、アルゴス、シラクサなど)で前6世紀末頃から導入されていた、僭主(独裁者)の出現を未然に防ぐ制度です。ギリシャ語では「オストラシズム」とも呼ばれますね。市民たちは、僭主になりそうな人物の名前を陶片(オストラコン)に記し、アゴラ(広場)で投票を行いました。そして一定数の票を集めた人物は、10年間の国外追放処分となる仕組みでした。
「追放」と聞くと過酷な制度のように思えるかもしれませんが、陶片追放は刑罰とは異なり、対象者の財産や市民権は失われず、期限が過ぎれば普通に帰国することができたのです。ある意味、「政治的クールダウン期間」を設けるようなものだったとも言えるでしょう。
それでは、この陶片追放がどのように生まれ、どのように運用されていったのか、詳しく見ていきましょう!
|
|
|
|
|
|
陶片追放の歴史
① 陶片追放の誕生と背景
陶片追放制度が生まれた背景には、アテナイの政治的混乱がありました。前6世紀末までのアテナイは、しばしば僭主(ティラノス)による独裁政治が行われており、特にペイシストラトス(前600頃 - 前527)やその息子ヒッピアス(前570頃 - 前490)は、その典型例です。
ペイシストラトスは一見すると民衆に人気のある政治家でしたが、実際には武力を背景に政敵を排除し、独裁体制を築いていました。彼の死後、息子のヒッピアスが後を継ぎますが、圧政を強めたため、市民たちはついに彼を追放します。その後、アテナイでは民主政が発展していきますが、「また僭主が現れたらどうする?」という不安は残っていたのです。
そこで登場したのが、陶片追放制度でした。この制度を導入したのは、民主政を確立したクレイステネス(前570頃 - 前508頃)です。彼は、一定の手続きを経れば、市民の合意によって独裁の芽を摘むことができるシステムを考案したのですね。
② 陶片追放の仕組みと運用
陶片追放が行われる手順は、比較的シンプルでした。
- まず、市民たちが「今年、陶片追放を実施するかどうか」を決める投票を行います。
- 実施が決まると、市民はアゴラ(中央広場)に集まり、陶片(オストラコン)に僭主になりそうな人物の名前を書き込みます。
- 6,000票以上の票を集めた人物は、10年間の国外追放となります。
投票に使われた陶片(オストラコン)は、当時の遺跡から多数発見されており、有名な政治家の名前が刻まれたものも残っています。
ただ、この制度が頻繁に使われたわけではありません。導入された当初(前5世紀初頭)は、政治的な対立が激しい時期だったため活発に実施されましたが、次第に形骸化し、前4世紀頃にはほとんど行われなくなっていったのです。
③ 陶片追放の衰退と終焉
陶片追放が次第に使われなくなった背景には、アテナイの政治状況の変化があります。
最も決定的だったのは、ペロポネソス戦争(前431 - 前404)によるアテナイの衰退です。この戦争でアテナイはスパルタに敗れ、民主政が大きく揺らぎました。さらに、戦後には寡頭派(貴族中心の政治を支持する勢力)と民主派の対立が激化し、もはや陶片追放のような「平和的な政治的調整」の余地がなくなってしまったのです。
また、陶片追放は本来「僭主の出現を防ぐため」の制度でしたが、やがて政争の道具として利用されるようにもなりました。たとえば、ライバルを排除するために虚偽の情報を流し、特定の政治家を追放に追い込むケースも出てきたのです。このように、制度の本来の目的が形骸化していったことも、衰退の一因となりました。
|
|
|
陶片追放の利点と欠点
利点
陶片追放の最大のメリットは、「独裁を未然に防ぐ仕組みがあった」という点ですね。市民が政治の行方を見守り、「危険だ」と判断した人物を合法的に排除できる制度は、当時としては画期的だったのです。
また、追放された人物の財産や市民権はそのまま維持され、10年後には帰国できるため、政治的な殺戮や粛清に比べればかなり穏やかな方法だったと言えます。
欠点
しかし、陶片追放には欠点も多くありました。
一つは、「本当に僭主になる可能性がある人物」だけでなく、「単なる人気者」や「政治的ライバル」まで追放される可能性があったことです。実際、アテナイの英雄であったテミストクレス(前524頃 - 前459頃)や、優れた改革者であったアリステイデス(前530頃 - 前468頃)も、政治的な対立から陶片追放されてしまいました。
また、後期になると制度自体が形骸化し、単なる派閥争いの道具として利用されるようになってしまったのです。
|
|
|
陶片追放で追放された人物一覧
実際に陶片追放によってアテナイを去ることになった著名な政治家たちを見ていきましょう。彼らの中には、本当に「僭主になりかねない危険な人物」もいれば、政治的対立や嫉妬によって追放された者もいました。この制度が必ずしも公平に機能していたわけではないことが、彼らの運命からもうかがえますね。
ヒッパルコス
ヒッパルコスは、アテナイで僭主政治を行ったペイシストラトスの親族として、民主派に警戒されていました。彼自身が独裁者になろうとしていたわけではありませんが、血筋ゆえに民主政の妨げになると考えられ、追放されてしまったのです。
当時、ペイシストラトスの息子ヒッピアスがアテナイで圧政を敷いていましたが、最終的にはスパルタの介入によって追放されます。その後、アテナイではクレイステネスによる民主改革が進められ、その一環として陶片追放が導入されました。ヒッパルコスが追放されたのも、この流れの中で「旧体制の関係者を排除する」という意図があったのでしょう。
アリステイデス
アリステイデス(前530頃 - 前468頃)は、アテナイの有力な政治家であり、特に財政・軍事面で優れた手腕を発揮した人物です。しかし、彼は政敵であるテミストクレスと対立し、ついには陶片追放にかけられてしまいます。
彼の追放にまつわる有名な逸話があります。投票の日、市民の一人がアリステイデス本人と気づかずに「すまないが、この陶片に『アリステイデス』と書いてくれないか?」と頼みました。理由を尋ねると、その市民は「彼のことはよく知らないが、『正義のアリステイデス』なんて呼ばれているのが鼻につくからさ」と答えたそうです。要するに、彼は善政を行っていたにもかかわらず、単なる人気投票のような形で追放されてしまったのですね。
もっとも、アリステイデスは後にアテナイへ帰還を許され、ペルシャ戦争での活躍を通じて名誉を取り戻しました。
テミストクレス
テミストクレス(前524頃 - 前459頃)は、アテナイの軍事戦略家として歴史に名を残しました。彼の最大の功績は、ペルシャ戦争中のサラミスの海戦(前480年)で、巧みな戦略によってアテナイを勝利へと導いたことです。
しかし、戦後、彼の人気が急上昇すると、これを快く思わない者たちが出てきました。特に、貴族派の政治家たちは、テミストクレスが平民の支持を得て力を強めることを恐れました。そこで、彼を危険視する声が高まり、陶片追放が実施されたのです。
追放後、テミストクレスはアテナイを去り、最終的にはペルシャ帝国に亡命しました。なんと、かつて戦った相手であるペルシャ王の庇護を受け、その下で生涯を終えたのです。戦争の英雄が、敵国で余生を過ごすというのも、なんとも皮肉な話ですね。
キモン
キモン(前510頃 - 前450頃)は、アテナイの指導者として強い影響力を持っていました。彼はアテナイの軍事的発展に貢献し、ペルシャ戦争後にはギリシア諸都市を率いる存在として活躍しました。 しかし、彼には一つ大きな問題がありました。それは「親スパルタ的な政策」を取っていたことです。当時、アテナイとスパルタは徐々に対立を深めており、キモンの姿勢は多くの市民にとって「時代遅れの考え方」に見えたのですね。
やがて、アテナイの政治はスパルタと対立する方向へとシフトし、キモンの立場は危うくなります。結果として、彼は陶片追放にかけられ、国外追放となりました。
もっとも、彼の追放は長くは続かず、後に復帰が認められ、最終的にはアテナイ軍を率いて戦場で命を落としました。彼は追放されたとはいえ、アテナイのために尽くし続けたのです。
こうして見てみると、陶片追放の対象者には、単なる「独裁者候補」だけでなく、「優れた政治家」や「戦争の英雄」までもが含まれていたことがわかります。アリステイデスやテミストクレスのように、実際にはアテナイの発展に大きく貢献した人物ですら追放されてしまうこともありました。
このことからも、陶片追放は必ずしも公正な制度ではなく、時には政治的駆け引きや嫉妬によって歪められることもあったのです。最終的にはこうした問題が積み重なり、陶片追放制度は徐々に廃れていきました。
色々と問題があったとはいえ、陶片追放制度が「民主政を守るための試み」であったことは確かです。現代の民主主義においても、「権力が集中しすぎないようにする仕組み」は重要ですよね。そう考えると、陶片追放は古代ギリシアが生んだ、ある意味で先進的な制度だったと言えるのではないでしょうか?