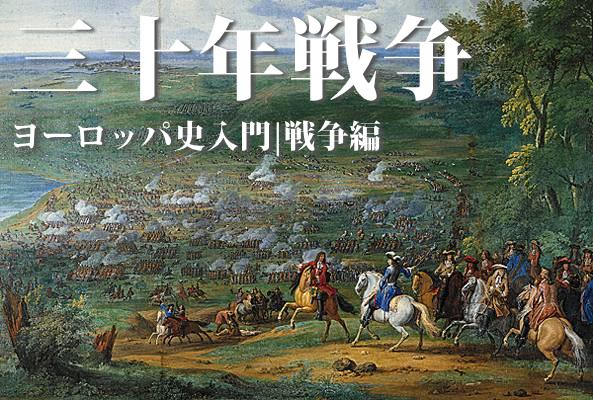

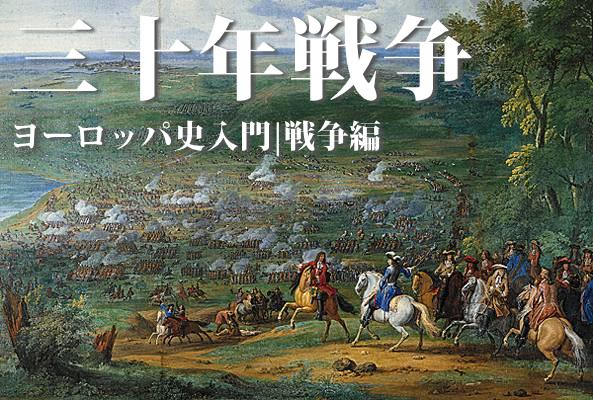
三十年戦争

三十年戦争の戦いの一つ「白山の戦い」
三十年戦争は、1618~1648年の30年にわたり、神聖ローマ帝国(ドイツ文化圏)を舞台に行われた「最後で最大」といわれる宗教戦争です。講和条約のウェストファリア条約により、15世紀末から始まっていた「主権国家体制への移行」がほぼ完了したという点で、ヨーロッパ史上でも非常に重要な意味を持つ戦争になりました。
|
|
|
|
|
|
三十年戦争の特色
この戦争は、きっかけこそ神聖ローマ帝国領内の宗教紛争でしたが、外国の介入もあり、徐々に政治的利害を優先する国際紛争という性格が強くなっていきました。そのため終盤では「カトリックのフランスが、プロテスタントのスウェーデンを支援する」という、宗教的にはありえない状況が生まれています。
|
|
|
三十年戦争の原因
ルターの宗教改革(1517年~)以来、新教vs旧教の宗教紛争が欧州全土で繰り広げられていましたが、少なくともドイツではアウグスブルクの宗教和議(1555年)で一応の終息はしていました。しかしこれで不平等が完全に解消されたわけではなかったので、その後対立が再燃し、1608年に新教連合ウニオン、1609年には旧教連盟リガを結成されるなど、またも緊張が高まっていたのです。
そんな中、カトリックのフェルディナント2世が神聖ローマ皇帝に選出され、ドイツ圏の宗教的統一を目指し、プロテスタントの弾圧を開始。これに対し、ボヘミア(現チェコ)のプロテスタントが反乱(プラハ窓外放出事件)を起こしたことがきっかけで、三十年戦争の火蓋が切って落とされたのです。
|
|
|
三十年戦争の戦い
三十年戦争(1618~1648年)は、宗教的対立と政治的野心が絡み合ったヨーロッパの大規模な紛争でした。この戦争は、神聖ローマ帝国内のプロテスタントとカトリックの対立に端を発し、次第にヨーロッパ全土を巻き込む国際的な戦争へと発展しました。以下は、戦争の4つの主要な局面についての解説です。
ボヘミア・プファルツ戦争(1618~1623年)
戦争の発端は、1618年のプラハ窓外投擲事件にあります。ボヘミアのプロテスタント貴族がカトリックの神聖ローマ皇帝フェルディナント2世に反発し、反乱を起こしました。これにより、ボヘミア王位を巡る争いが勃発し、プロテスタント陣営はプファルツ選帝侯フリードリヒ5世を新たな王として擁立しました。
主な戦闘は1620年の白山の戦いで、この戦いでプロテスタント軍は神聖ローマ皇帝軍に敗北し、ボヘミア反乱は鎮圧されました。その後、プファルツ地方もカトリック軍に制圧され、フリードリヒ5世は「冬の王」と揶揄されながら亡命を余儀なくされました。この段階では宗教戦争の色彩が強く、プロテスタントとカトリックの間の緊張が高まりました。
デンマーク戦争(1625~1629年)
プロテスタント側を支援するため、デンマーク王クリスチャン4世が戦争に介入しました。彼は神聖ローマ帝国内のプロテスタント諸侯を支援しつつ、北ドイツで勢力を拡大しようとしました。しかし、皇帝軍は優れた司令官ヴァレンシュタインの指揮のもと、クリスチャン4世の軍を撃破しました。
1629年に結ばれたリューベック条約により、デンマークは神聖ローマ帝国内の問題に干渉しないことを約束し、戦争から撤退しました。この時期には、皇帝フェルディナント2世が復旧勅令を発布し、プロテスタントによって奪われた教会財産をカトリックに返還するよう命じましたが、これがさらに宗教的対立を深める結果となりました。
スウェーデン戦争(1630~1635年)
戦争はスウェーデン王グスタフ・アドルフの登場で新たな局面を迎えました。グスタフ・アドルフは、プロテスタント勢力の擁護者として参戦し、北ドイツを舞台に神聖ローマ皇帝軍に対抗しました。彼は1631年のブライテンフェルトの戦いで皇帝軍に大勝し、スウェーデン軍の進撃はヨーロッパに衝撃を与えました。
しかし、1632年のリュッツェンの戦いでは、スウェーデン軍が勝利したものの、グスタフ・アドルフ自身が戦死しました。この後、スウェーデンの勢力は後退し、プロテスタント勢力は再び不利な状況に立たされます。
フランス・スウェーデン戦争(1635~1648年)
1635年以降、フランスが直接介入し、戦争は宗教的な対立から国家間の勢力争いへと性格を変えました。カトリック国であるフランスは、スペインや神聖ローマ帝国の抑制を目的にプロテスタント側に立ち、スウェーデンと同盟を結びました。
|
|
|
三十年戦争の講和条約
三十年戦争の講和条約として、1648年、ドイツのウェストファーレンにてウェストファーレン条約(英名はウェストファリア条約)が締結されました。ドイツの領邦国家も1国と数え、計66か国が参加しています。
この条約によりフランス・スウェーデンは領土を大きく拡大。スイスとオランダの独立が正式に承認され、神聖ローマ帝国内での信仰の自由(カルヴァン派の容認)も認められました。
またこの条約により神聖ローマ帝国を構成する領邦が主権を持ち、神聖ローマ帝国は名目だけ残し、国家としてのまとまりを失ってしまったので、別名「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と言われています。
|
|
|
三十年戦争の影響

三十年戦争の講和条約ウェストファリア条約の締結場面
三十年戦争は、ヨーロッパ全土に広範な影響を及ぼした大規模な戦争であり、1648年のウェストファリア条約による終結は、ヨーロッパ近代史における重要な転換点となりました。この条約は、宗教的・政治的な秩序の再編成をもたらし、各国の命運に大きな影響を与えました。
新たな強国の台頭
ウェストファリア条約によって、ヨーロッパの勢力図が一新されました。
フランス
アルザス地方を獲得したフランスは、ブルボン朝の下で中央集権化が進み、大陸ヨーロッパ最強の国家としての地位を確立しました。この戦争を機に、ハプスブルク家に代わる新たな覇権国家として台頭し、後のルイ14世の時代にはさらにその影響力を拡大します。
スウェーデン
バルト海沿岸地域(西ポンメルンなど)を獲得したスウェーデンは、北欧の覇権国家としての地位を確立しました。スウェーデンの軍事力と影響力はピークに達し、バルト海を「スウェーデンの湖」と称するほどの支配を誇りました。
オランダとスイス
ウェストファリア条約で、オランダ(ネーデルラント連邦共和国)とスイスは神聖ローマ帝国から正式に独立が認められました。オランダは以後、海洋貿易で繁栄し、「黄金時代」を迎えます。一方、スイスは中立を基本とする独自の国家体制を確立しました。
神聖ローマ帝国の衰退
戦争によって最も大きな打撃を受けたのが、主戦場となった神聖ローマ帝国でした。
人口減少と経済的荒廃
戦争の戦闘行為に加え、略奪や疫病が相次ぎ、800万人以上が死亡したとされています。これは当時の帝国内人口の約20%に相当し、多くの地域が経済的・社会的に壊滅しました。
領邦国家の独立性の確立
ウェストファリア条約では、神聖ローマ帝国の構成領邦に主権が認められ、各地の諸侯が事実上独立した政策を行う権利を持つようになりました。これにより、神聖ローマ帝国という枠組みは形式上存続しましたが、実質的には統一性を失い、権威の低下が決定的となりました。この分裂は、ドイツ地域の近代化の遅れを招く要因となりました。
宗教と政治の分離
ウェストファリア条約は、宗教戦争の終焉を象徴する条約とされています。まずカトリックとプロテスタントの対立は沈静化し、信仰の自由が一定程度保証されるようになりました。条約では、神聖ローマ帝国内での各領邦君主が、領内の宗教を自由に選択できる「領邦主義」(キリスト教のカトリック、ルター派、カルヴァン派の三宗派の承認)が定められたのです。そして宗教を国家の統治とは切り離し、現実的な国家間の利益が重視される国際政治の基盤が築かれるようになりました。これにより、ヨーロッパは宗教的な対立よりも政治的・経済的な利害を中心に動く時代へと移行したのです。
国際関係と近代外交の始まり
ウェストファリア条約では、各国が独立した主権国家として承認される新しい国際秩序が形成されました。これにより、領土主権の概念が定着し、近代外交の基礎が築かれました。この条約を契機に、外交官制度や国際法の発展が促進され、現在の国際関係の基本的な枠組みが形作られたのです。
三十年戦争とウェストファリア条約は、ヨーロッパに新しい秩序をもたらしましたが、その過程でドイツ地域を中心に莫大な犠牲を生み出しました。戦争が終結した後のヨーロッパは、強国による主権国家体制が確立され、近代的な国際社会の始まりとなりました。一方で、戦争による痛手が残したドイツ地域の荒廃は、長期間にわたって影響を及ぼし、19世紀のドイツ統一に至るまでその傷跡を残すこととなりました。
|
|
|


